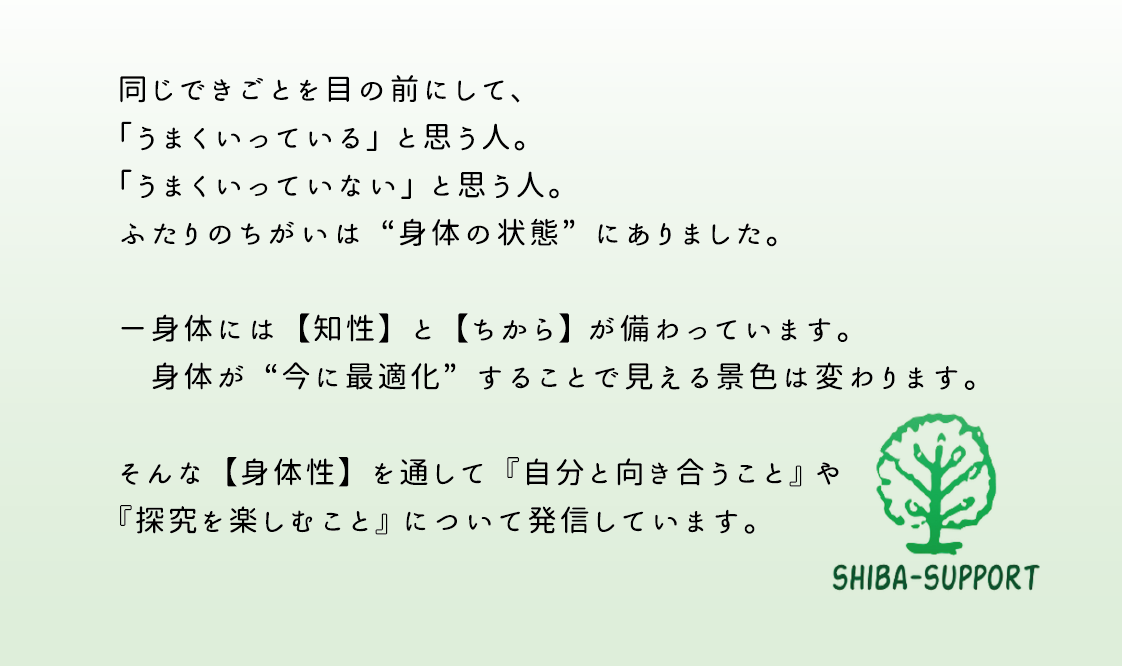なぜ“宗教肯定派カウンセラー”なのか?
私が
“宗教肯定派カウンセラー”
と名乗っているのには
ふたつの理由があります。
●カウンセラーの宗教観がわからず、
一歩踏みだせない方へ
わかりやすく意志表示をするため。
それがひとつの理由です。
私自身が
自分の生き方に悩んでいたとき、
誰に相談したらいいのかわからず、
相談すべきことなのかもわからず、
意を決してカウンセリングを受けて
みたことがありました。
一人目のカウンセラーさんには、
宗教のことについて話せませんでした。
きっと
私のなかの絡まったものは、
宗教や信仰というものと
向き合わないことには
解きほぐすことはできなかったのに、
その核心に触れることができず、
上澄みをすくったような会話に
始終していまいました。
二人目のカウンセラーさんには
思い切って、
この核心について話してみることに
しました。
ですが、
恐らくそのカウンセラーさん自身に、
宗教が身近にあるという経験が
なかったようで、
私のなかの絡まりを
単なる『マインドコントロール』
のように判断されてしまい、
私には寄り添ってくれるけれど、
その寄り添いのなかには、
宗教への遠回しなバッシングが
含まれていました。
きっと
カウンセラーさんとの
相性もあるでしょうし、
しかたのないことだったのですが、
私のなかに相談する前よりも
大きなざらつきが残る結果と
なりました。
他にも
あきらかなカルト宗教を
脱会させてくれるような
カウンセリングや、
同じように宗教による生きづらさを抱えた
経験のあるカウンセラーさんが
寄り添ってくれるカウンセリング
はありましたが、
それらも“宗教否定派より”であり、
「ちょっとちがうなぁ・・」
という感覚はぬぐえませんでした。
過去の私のような方にとって、
“宗教肯定派”というわかりやすい看板は
安心感にも、
ちょっと一歩踏みだしてみよう、
という気持ちにもつながるのではないか
という思いからこの肩書を名乗っています^^
そうでない方からすれば
この肩書は少し奇妙かも
しれないですね(笑)
そして、
●お互いに自分の宗教をもっている場合、
カウンセリングがスムーズに
進みやすいことを実感するから。
それがもうひとつの理由です。
私自身も実感している
ことなのですが、
もっとわかりやすく
表現された文章があったので
ご紹介しますね^^
下記の文章は、
東山 紘久さん(心理療法家)と
加藤 廣隆さん(石像寺・住職)という
お二人の共著からの引用です。
東山氏は京都大学の教授などを
歴任される臨床心理士であり、
加藤氏は京都・西陣にある
石像寺(通称・とげぬき地蔵)
というお寺のご住職です。
石像寺には、
お寺の一角に
カウンセリングルームがあり、
そこにはさまざまな
悩みを抱えた人が訪れていました。
そんなお二人の
心理療法家としての視点、
宗教家としての視点から
カウンセリングと宗教について
つづられた一冊です。
私のところへはいろいろな宗教をもっている方が、カウンセリングを受けにこられます。カトリックの神父さんや牧師さん、お寺の住職、新興宗教や新々宗教を信じておられる方まで多様です。東山は宗教をもっている人の方が、カウンセリングを行いやすいのです。
これらの方々は、みなさん自派の宗教の中で、霊的指導者や宗教指導者をおもちです。しかし私のところへ来られるときは、ご自身の指導者との対話や関係が悩みを解決するように働いていないときです。
自分の宗教をもっているクライアントやカウンセラーは、相互の転移・逆転移を自分の神仏に投影することによって、治療関係の複雑さを回避できます。それは神仏に関係を投影することによって生身同士の関係を回避できるからです。
ここでの難点は、カウンセラーとクライエントが同じ神仏をもっている場合です。神仏は心理学的には、己の魂の象徴化されたものですから、心理学的には本来同じ神仏でも意味は異なっているのです。しかし、同じ神仏だと、魂の象徴化されたものが混同を起こし、カウンセラーとクライエントの心の独立性が危うくなります。外から客観的に見るとなんとも表現がつかないような宗教集団がもつうさん臭さを感じられることがあるかと思いますが、これは魂の混交がもたらせる匂いといえましょう。
文章はとても難しいのですが、
そこに表現されていることは
とても納得感があり、
引用させていただきました。
引用にある
「相互の転移・逆転移」とは
精神分析学の言葉のひとつです。
カウンセリングのなかで生じた感情や思い、
考えをカウンセラーとクライエントが
お互いに向けあってしまう現象のことをいいます。
カウンセリングの場だけでなく、
介護の現場でも起こるような現象です。
たとえば、
カウンセリングが進むにつれて
かつての誰かを憎む気持ちが
思いだされたとき、
無意識のうちに目の前のカウンセラーに
憎しみを抱くようになったり、
逆に
クライエントの抑え込まれた感情が
カウンセラーに伝わり、
カウンセラーの抑圧していたものが
刺激されてクライエントに歪んだ対応を
してしまったりします。
転移や逆転移は
お互いの無意識のところで生じている
ものであり、だからこそカウンセラーは
つねに自身の感情を観察し、
その洞察力を高める訓練をしています。
もちろん私自身も
その訓練は怠っていないのですが、
引用にあるように、
お互いに宗教をもっていると、
不思議とこの「転移・逆転移」
というものが起こりにくく、
カウンセリングが進みやすいと感じます。
次の記事で詳しく
書いてみたいと思うのですが
宗教をもつ人、信仰心のある人というのは、
本人の自覚があるかどうかにかかわらず、
どこか自己の領域とはちがうところへ
自分の持ち物を預けておくことが
やりやすいのではないかと思います。
私は勝手に
“心のセーフティネット”
と呼んでいるのですが、
なにかに対する畏敬の念、
簡単にいってしまうと《感謝の気持ち》
のようなものがあると、
自己のなかにある、ある程度のものを
委ねてしまえる・・という特徴があり、
お互いにそれができていることで、
「転移・逆転移」のような混濁した
状況をさけられるのかもしれません。
決して
「転移・逆転移」がただネガティブなだけの
ものなのではなく、
カウンセラーとクライエントとの関係に
ポジティブに作用することもあるので、
起こってはいけない現象ではないのですが、
カウンセリングを進めるうえで、
お互いが異なる宗教をもっていることは
プラスに作用するといえます。
自分が大切にしているものを
“自己開示”する、という意味でも
とても有効なのかもしれません。
そして引用にあるように、
“ご自身の指導者との対話や関係が
悩みを解決するように働いていないとき”
というのは、
このブログを読んでくださっている方なら
経験があるのではないでしょうか。
なんとなくありますよね^^;
どんなに尊い教えのもとでも、
このようなときというのは、
そのときは悩みが解消されたように
思えても、いつも着地点が同じ
ように感じられまたしばらくすると
モヤモヤがでてきてしまうことがあります。
どうしても
同じコミュニティのなかにいると、
相談される側も“あるべき”着地点に
結論をもっていかなければいけない、
という無意識の義務感が働いてしまう
ことがあります。
その人が悩んでいるのは
宗教によるしがらみや暗黙のルールによる
息苦しさである場合でも、
結局はその教えの延長線上にある
アドバイスが返ってきてしまうことも
少なくありません。
“わかっているけど、
今はそれがむずかしいんだ・・”
という歯がゆい思いを抱え続け、
さらにその抑圧された思いは
気づけば生きづらさにつながって
いってしまいます。
“わかっているけど、
今はそれがむずかしいんだ・・”
という歯がゆい思いが示しているのは、
その宗教による恩恵をたしかに感じている、
けれども少ししんどさを感じているんだ、
という心の葛藤です。
そんなとき、
異なる宗教をもつ相手に話してみる、
というのはとても効果的な方法です。
お互い異なる宗教をもちながら、
その価値観を尊重されるという経験は、
なんともいえない安心感があり、
いつものコミュニティのなかでは
打ち明けられないことも、
案外話せてしまうものです。
宗教肯定派カウンセラーとして
提案する方法は、
その教えの延長線上のにあるものではなく、
心理的・身体的なアプローチです。
当初は、
宗教によるしがらみや
生きづらさによる苦しみが
悩みの種だと思っていたのに、
もっと根本的なところに原因が
あった、ということもあります。
すべては、
その人が“本質的な自分”に
立ち返ったとき、
なにがでてくるか、
というところにかかっています。
宗教や信仰のある
その環境から受けた恩恵をもう一度
思いだすお手伝いもできます。
また
“その環境との距離のとり方”
についても一緒に考えていくことが
できます。
さらには、
“本質的な自分”が見えてきたとき、
思いもよらない人生の目標や夢が見つかる
ことも少なくありません。
そうして自然と
「自分のための人生」が始まっていくと、
今度は宗教・信仰によって受けてきた恩恵を
最大の武器にして進んでいくこともできます。
その恩恵とは、
【信仰心】と表現される、
“信じるちから”であったり、
“感謝の気持ち”であったり、
“まもられている感覚”であったり、
さまざまです^^
また
2代目以降の信者さんがすでにもっている
【リソース(強み)】と
「自分のための人生を生きる」ことの
【メリット】について、
次の記事で詳しくお話していきたいと
思います^^
今日も最後まで
お読みくださってありがとうございます。
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^