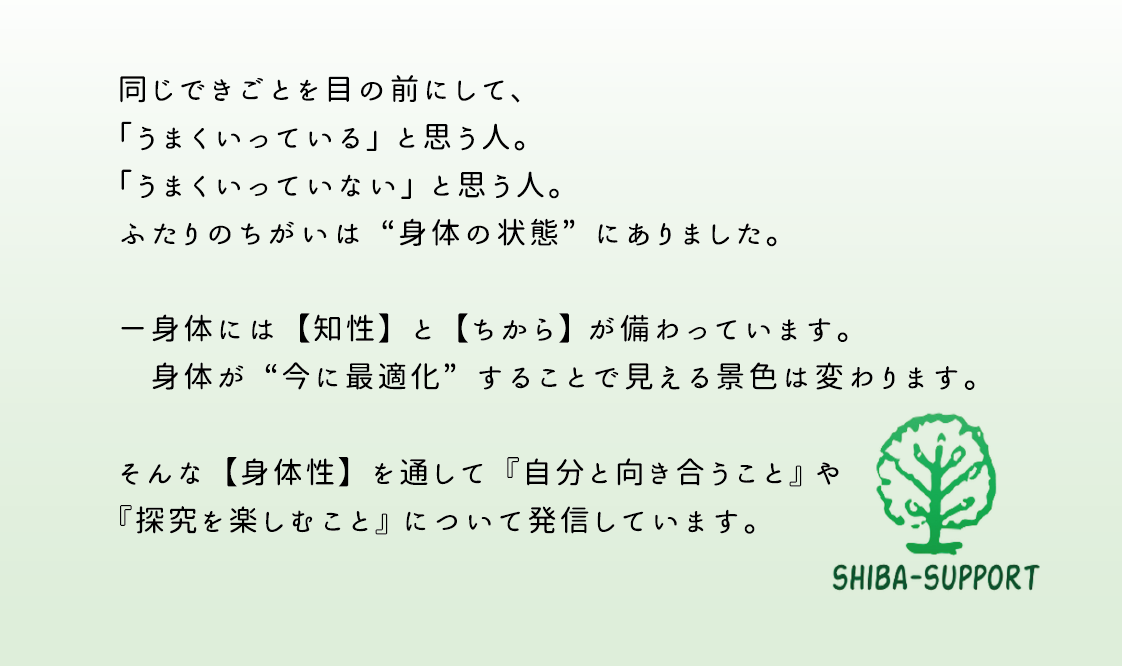-Contents-
【身体感覚】に慣れていく
それでは、
ソマティック(身体性)な探究を
深めていただけるような方法を
少しずつ書いてみたいと思います^^
前回の【本質編】でも
お伝えしておりましたが、
どんなときにも、
身体の細胞たちへの
「ありがとう」と
「ごくろうさま」というスタンスが
一番大切であり、それさえあればなんでも大丈夫です(笑)
“感じること”に抵抗があったり、
【身体感覚】に慣れていないうちは、
『ひとりぼっちで過ごしてみる』
『自分が感じていることを知ろうとする』
ということをなんとなくしてみるだけでもOKです。
(※それぞれリンクを貼っているので、
過去記事をご参照くださいね^^)
そして、
“感じること”に慣れてきたら、
ストレッチやヨガなど日頃の運動で
『動的瞑想』をするのもおすすめです。
————
たとえば
ストレッチや筋トレをするときに…
《伸ばす》のではなく、
《伸びていることを感じてみる》
《伸ばす》というのは、
顕在意識的なMind主体のアプローチです。
(【思考】によるコントロール)
《伸びていることを感じてみる》
というのは、
潜在意識的なBody主体のアプローチです。
(【身体感覚】による最適化)
————
こちらの記事でも書いていたように、
“意識を向けるだけ”
“気づいてあげるだけ”
で身体が抱えてくれている
余計なデータはクリアされていきます^^
【思考】を鎮めるということ
【身体感覚】を育てることとともに、
【思考】を鎮めることも大切です。
これまでお伝えしてきたように、
【思考】が考えていることは、
“愛されるためには?”
つまり、
“他者からの承認を得るためには
どうすればいいか?”
という発想から始まっているので、
私たちが本当に望んでいることとは
かけ離れていることも少なくありません。
それでも私たちは、
強迫的に【思考】をフル稼働してしまいます。
その原因のひとつは
“愛されなければ価値がない”
という刷り込みです。
その刷り込みに無意識のうちに
振り回されて強迫的になってしまいます。
そして
【思考】フル稼働のもうひとつの原因は、
『情報量』です。
私たちはこの『情報量』にすっかり
慣れきってしまっていますが、
17世紀のイギリス人の一生分の情報量が
私たちの一週間分の情報量に相当する、
といわれています。
これは驚きのデータです。
これだけの情報を処理しているのだから、
いつのまにか無意識のうちに、
【思考】フル稼働になってしまうのも
当然のことですよね。
“身体”の声を聴くためには、
【身体感覚】を育てることはもちろん、
【思考】を鎮める、ということも実は大切なポイントなんです。
それくらい【思考】はやかましいんですね^^;
こんなにも【思考】がフル稼働する以前の
人間であれば、わざわざ【身体感覚】を
養ったりしなくても、普通にしているだけで
そこにアクセスできたのかもしれません。
でも私たち現代人はそうもいかないですよね。
【思考】がグルグルしてしまうとき、
身体はきゅっときゅうくつで
呼吸も浅くなりがちです。
【思考】がグルグルしてしまうとき、
その根底にあるものは、
“恐れ”や“不安”なので、
私たちは“いやな感じ”を体感し続けなければいけません。
こうした“体感”がまたさらなる“体感”を
引き寄せるので、
“いやな感じ”の無限ループです。
だからまずは、
【思考】のグルグルを鎮めていきましょう。
今回の記事では、
【思考】のグルグルをストップできる
スイッチとなる方法を2つご紹介しますね^^
<方法①>ジャーナリング
“身体”を使った瞑想、
「書く瞑想」
ともいわれるジャーナリングです。
必要なものは、
紙とボールペンだけでOK。
時間を5分と決めて、
時間がくるまでひたすら、
自動書記のように思いつくままに書き続けます。
“お腹すいたー。
何食べたい気分かな?
夕方は予定あるから
いっぱい食べないほうがいいかも。
あ、クリーニング屋さん水曜休みだっけ。
あ~やっちゃった。
昨日夢でみたのなんだっけ、
あ、これいいかもって思ったんだけど
思いだせないなー。
どうしよう書くことなくなってきた。
どうしよう、どうしよう、
あ、これ終わったらトイレ行こう…”
こんな感じで、
とにかく書き続けます。
5分終わるまで書き続けます。
いわゆる脳汁ってこんな感じ?
と思えるような感覚になってきます(笑)
でもこれにもちゃんと意味があります。
【思考】のグルグルの原因は、
顕在意識で考えていることの
もう少し深くにあるものなので、
自覚できる上澄みのものから
出し尽くしていきます。
そうすると必然的に、
その下の層にあるものがでてくるので、
それだけで【思考】のグルグル
(=悩みごと)が解決されることもあります。
また
「書く瞑想」と呼ばれるだけあって
集中力UPにも効果抜群です。
さらに
【思考】を可視化する、という
『メタ認知』を高める作業でもある
ので自己肯定感も上がっていきます。
(このことについてはまた記事を書いて
みたいと思います^^)
さらにさらには、
【身体感覚】がひらかれて、
本質的な自分の本音などがわかるように
なってくると、インスピレーションや直感
がたびたびでてくるようになります。
ジャーナリングに慣れていると、
こうした発想がふわっと湧いてきたときに
“ふわっと湧いたものを言語化する”
ということがやりやすくなっているので
湧いてきたものを形にしやすくなる、
という特典つきです^^
ちょっと面倒だな…
と思われがちなジャーナリングですが、
【思考】を鎮めることだけでなく、
長期的なメリットもかなりあるので、
ぜひやってみてくださいね。
このジャーナリングの習慣だけで
収入を5倍にした強者もいるそうですよ(笑)
私はもう時間制限はあえて決めず、
『もやもや、もわもわ』が浮上してきたら、
パッと書き尽くすようにしています。
そうすると、
ぐるぐる反芻思考に陥らずに済むので、
“いい気分”でいることがニュートラルに
なっていきます。
(またこの“気分”というぼんやりとしたものが
めちゃくちゃ重要なんです!
“気分”についても記事を書いてみたいと思います^^)
<方法②>呼吸と動きをともにするソマティックワーク
私たちの身体は、
“ゆったりとした呼吸”と
“ゆったりとした動作”を一緒にすることで、
【思考】がしにくくなるようにできています。
今度は、
そんな身体の機能を利用したワークです。
①ゆったりと力をぬいて座ります。
②下げた両腕を前方から上にゆっくり上げます。
(※このとき息を吸います)
③両腕を上から横にゆっくり下ろします。
(※このとき息を吐きます)
④上記①~③の動作と呼吸を繰り返します。
⑤そして、
腕に感じる感覚を味わってみます。
呼吸は口からでも鼻からでも
ご自身がやりやすい方法でOKです。
腕の感覚を感じてみるとき、
“ちょっと二の腕のあたりが
重いな・・・”
のような気づきがあることは、
もちろんOKです。
ただ、
そんなふうに言葉にすると、
【思考】に戻ってしまいやすくなります。
できるだけ、
その“二の腕の重さ”の感覚にとどまってみてください。
【思考】にいきそうになるのを、
【感覚】にとどまろうとする。
(なんとなく《右脳》を意識してみます。
《右脳》を意識してみるだけでも、
思考は鎮まっていきます^^)
だんだんと、
その“二の腕の重さ”に変化が起こって、
身体のままに動く…という体験が起こってくるようになります。
これが【身体感覚】を育てることにつながり、
“身体”の声も聴こえやすくなっていきます。
このワークを実際にしてみると
わかるのですが、
【思考】がフル稼働していると
腕の動きと呼吸がスピーディになっていきます(笑)
腕の動きが早くなっているときは、
【思考】にひっぱられているだけなので
そのままにせず、“ゆっくり”とした動作にもどしていってくださいね^^
とても簡単でいつでもできるワークなので、
話し合いの場でちょっと煮詰まったとき、
みんなでこのワークをしてみるだけでも
意外な本音やアイデアがでてきやすくなったりします。
また記事を書きたいと思っていますが、
ソマティック(身体性)の探究の面白いところは、その探究が身体のことにとどまらないところです。
身体から余計な力が抜けていくほどに、
これまでにはなかったクリエイティブな
視点がもたらされます。
それは自分の内側のことだけでなく、
この世界や社会の在り方、
組織のことについてもみえてくるものがあるんですね。
【ソマティック(身体性)】×【組織づくり】
という領域がかなり注目されています^^
次回の記事では、
そんな領域の探究から見えてくる
ソマティック(身体性)と【男性性】
について書いてみたいと思います。
————
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^