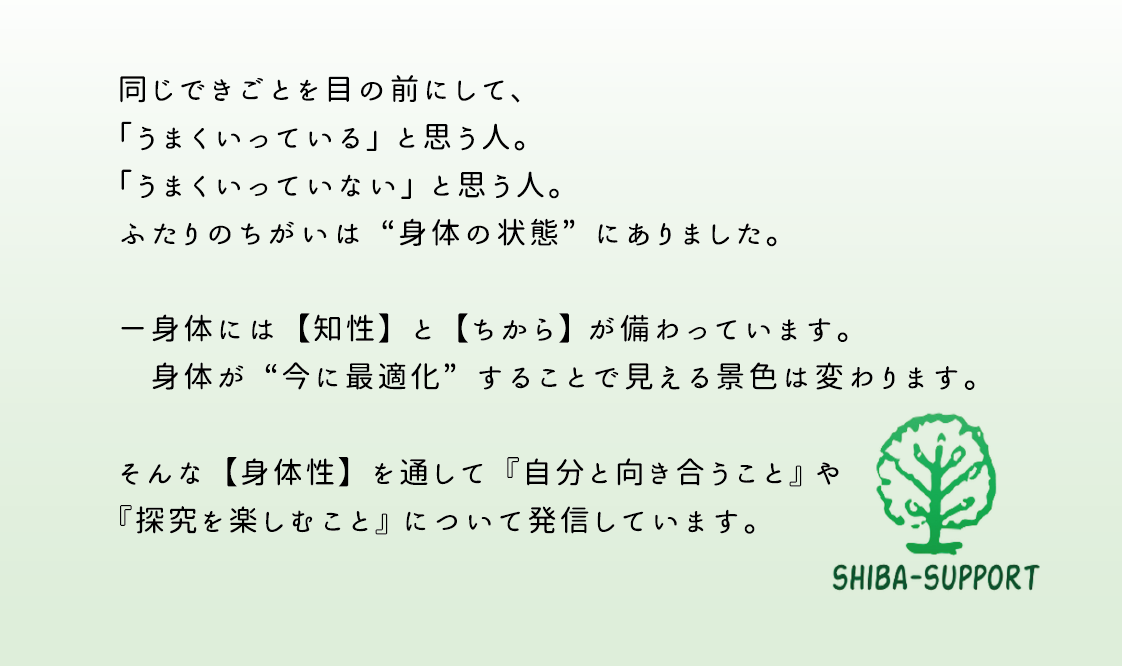-Contents-
“インナーチャイルド”とは?
前回の記事ででてきたような、
自分のなかで抑圧していた存在や、
未消化のままになってしまっている感情を
心理学の言葉では
【インナーチャイルド】と呼びます。
【インナーチャイルド】の存在によって、
大人になったその人の生き方や行動パターンが形成されていることがあります。
【インナーチャイルド】が
そのときに満たされなかった想いに
どうにか気づいて欲しがっているから、
同じような体験を繰り返してしまったり
苦しみや痛みを味わう状況を
選び続けてしまったり…
これは無意識に自分で選び、
体験しています。
無意識のなかに
【インナーチャイルド】の記憶
があるからですね。
私のようにイメージででてくる人もいれば、
実際にその感情が生まれたときのリアルな場面を思いだす人もいます。
たとえば恋愛で
自分を大切にしてくれないパートナーから
離れられない女性の場合。
そして自分と向き合ってみたとき、
その女性が小さかった頃、
周りの大人たちに
「〇〇ちゃんは末っ子で
まだ小さいからわからないよね~」
と言われてすごく傷ついていたことを思いだします。
そして、
いつも“みじめさ”を感じていたこと、
そのたびにお腹が痛くなっていたこと、
今パートナーにきつく当たられたときも
お腹を壊してしまうということ。
だから
“みじめさ”を感じさせる体験が
繰り返されていたんだ、
という気づきに至ります。
そんなインナーチャイルドの存在に
“気づいてあげる”
ただそれだけで、
すっとそのパートナーから離れる
ことができたりします。
「なんだ~。
私のなかにこういう自分がいたから、
ろくでもない人とばっかり
付き合ってしまってたんだ!」
ほかの複雑なことがからまって、
すぐに解決とはいかなくても
心の在り方はぐんと健全に
なっていきます^^
どんなご縁も
ちゃんと出会った意味があります。
それがどんな終わりでも、
「気づかせてくれてありがとう!」
と気持ちよく手を離せたら…
きっと、
その先には一歩進んだ未来が
待っています^^
そしてそのパートナーを
「ろくでもない人」
といえるのは彼女だけです。
なぜ、
彼は彼女にきつく当たってばかり
いたのでしょうか?
本当に気持ちがなくて、
彼女のことが好ましくないなら、
わざわざ時間をつくって
会ったでしょうか?
どうして好きなのに、
いつもつらく当たるのか?
“好き”という気持ちより、
どんなにひどいことをしても
好きでいてくれるかどうかに
ばかり気持ちが向いてしまうのは
どうしてなのか?
彼のなかにも、
きっと気づいて欲しい
なにかがあるのかもしれないですね。
ただ単純に、
そういう人だという可能性だってあります。
彼女を失った彼が、
そんな自分と向き合うか、
向き合いきらずに新しい人と
付き合ってまた大切な人を失う
という経験を繰り返すか、
それも彼のタイミングです。
無理やりに向き合わなくても、
無意識のうちに
一緒に乗り越えてくれそうな人を選び、
お互いが対等でありながら、
ちゃんと向き合っていけるという
タイミングがやってくることもあります^^
なんとなく、
【インナーチャイルド】の存在と
再体験のつながりが見えてきた
でしょうか。
たとえば職場で
男性の上司のどなり声を聞くと、
動悸がして仕事どころではなくなってしまう男性。
“となりの同僚はなんともないのに、
どうして自分だけ…”
と悩んでいます。
その男性が小学生だった頃、
父親に強く叱責されて
反抗することもできず、
こぶしをぎゅっとにぎって
それを耐え忍んでいました。
そう、
そのときに
“怖かった”という気持ちを抱えた
インナーチャイルドが、
大人になった男性に気づいて
欲しがっていたのです。
それに気づき、
寄り添ってあげると、
もう職場の上司の叱責が
怖くなくなっていました。
いずれも、
今の生きづらさの原因が過去の経験に
あることに気づかされていきます。
同じ状況や境遇であっても、
どれくらい傷つくのか、
どれくらい痛みになるのかは、
その人によってさまざまです。
誰の目にもあきらかな虐待だけが
【インナーチャイルド】
の原因ではありません。
例にあげた女性のような経験は、
きっとだれもがしてるようなことで、
周りの大人たちにも悪気はありません。
ただ、当時のその女の子はとても傷ついて
“みじめさ”を抱えることになりました。
でもそのとき、
その“みじめさ”に気づき、
その感情を丁寧にあつかってくれる人は
いませんでした。
そうすると、
その未消化の感情が、
【インナーチャイルド】として
大人になっても女性のなかに存在し続け、
その女性の生き方に特定のパターンを
もたらしていくんですね。
あまりにつらかったりすると、
本人は意識の上で
その出来事を忘れてしまっていたりします。
けれども、
37兆個とも60兆個ともいわれる
身体の細胞たちは、
私たちが自分に秘密にしていることも、
すべてちゃーんと覚えていて、
同じような場面に遭遇したときは
そのときと同じような身体の反応を
示していたりするんですね。
だから
身体の細胞へ意識を向けてあげることが、
その秘密を抱えている存在に出会うための
大切な第一歩です。
それは
【自己蔑視】や【自己否定】であったり、
一見するとネガティブでお邪魔虫のような
足をひっぱるような存在に思われがちです。
でも、
そんなふうに私たちの人生を邪魔したくて
そんなことをしているわけではありません。
ただ、気づいて欲しいだけなんです。
かつてとても悲しい思いをしたこと。
愛して欲しかったのに
愛してもらえなかったこと。
ずーっとその存在に気づかずに
がむしゃらに生き抜いて、
晩年に認知症になったお年寄りが
まるで幼い女の子のようなことを
言いだすことがあります。
これも【インナーチャイルド】の記憶です。
“インナーチャイルド”はネガティブな存在?
こうして言葉で表現すると、
その存在がとてもネガティブで
煙たいもののように感じられるかもしれませんね。
でもまったくネガティブなものではないし、
そもそも【インナーチャイルド】の記憶は、
勘違いによるものもたくさんあるんです。
お母さんとしては
そんなつもりがなかったのに、
赤ちゃんが「愛されてないんだ!」
と思い込んでそのままインナーチャイルドを
抱えてしまったりもします。
だから、
こうしたチャイルドの存在が見つかっても、
自分の育った環境を悲観する必要もないし、
本当に普通のことなんです。
見つけてあげられてよかった♪
くらいがいいかもしれません^^
またこの【インナーチャイルド】には
幼少期だけではなく、
10歳、20歳、30歳・・と
それぞれいろんな年齢のときに
生まれた記憶もふくまれています。
本当は傷ついていたのに、
なんでもないフリをして
感情にフタをしてしまうことって
大人になってもありますよね^^
どれだけもう気づききった!
と思っていても、
また新しい記憶が刻まれていることもあるし、逆にすべてに気づききる必要もないと言えます。
気づく必要があるときには、
ちゃんとサインを送ってくれます。
だから、
なにか
人生のなかで生きづらさを感じたとき、
違和感を抱いたとき、というのは、
彼らの存在に気づいてあげられる
絶好のチャンスであり、
新しい人生のステージが見えてきている、
ともいえるのです。
【インナーチャイルド】は、
私たちを邪魔したくて
存在しているのではなく、
むしろ私たちの傷を
一手に引き受けるようにして
重荷を背負ってくれていた存在です。
どれだけタフで頼りがいがあるんだろう
って思いませんか?
その存在に気づいて認めてあげる。
そして味方になってもらえると、
あら不思議!
自分でも知らなかった
自身のポテンシャルに気づいたり、
これまでとはちがう行動を
とってみることができたり、
チャイルドを抱えてくれていた
身体の部分がふっとゆるんで楽になれたり、
気づけば視点がひとつあがっています。
【自己受容】を経て、
【自己肯定】に至るというのは、
そういうことなんですね^^
自己肯定感という言葉が
よく聞かれるようになりましたが、
つまりは
“自分を知っていくこと”
ただそれだけのことです。
そして、
そのときは、
“でてきても大丈夫だよ”
という態度でいることが
本当に大切です。
たまにこうした
インナーチャイルドの概念を逆手に
とるようにして、
本人は無自覚でも
「どこにいるんだ?」
「なにがあって今自分は苦しいんだ?」
と探し回るようにしてしまうことがあります。
いわゆる犯人探しのような(笑)
これ、
逆の立場だったら
ちょっと嫌ですよね?
なにかあるなら、
ちゃんとでてきてくれます。
だからできるだけ身体をゆるめて、
身体の細胞たちを信頼して、
苦しみから距離をおくことに
意識をむけてみてくださいね^^
そして、
“自分らしく生きる”
ということの正体が、
do(どうするか)ではなく、
be(どう在るか)である、
ということを少しでも
体感して頂けると嬉しいです^^
※※【インナーチャイルド】は
心の奥深くに隠れていて、
あまり急に刺激したりすると
危険だという見方もあります。
今でも記憶にのこるような
虐待やいじめなどのサバイバル経験、
フラッシュバックなどの症状がある場合は、
カウンセリングを受けるなどサポートのもと
向き合うことをおすすめしています。※※
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^