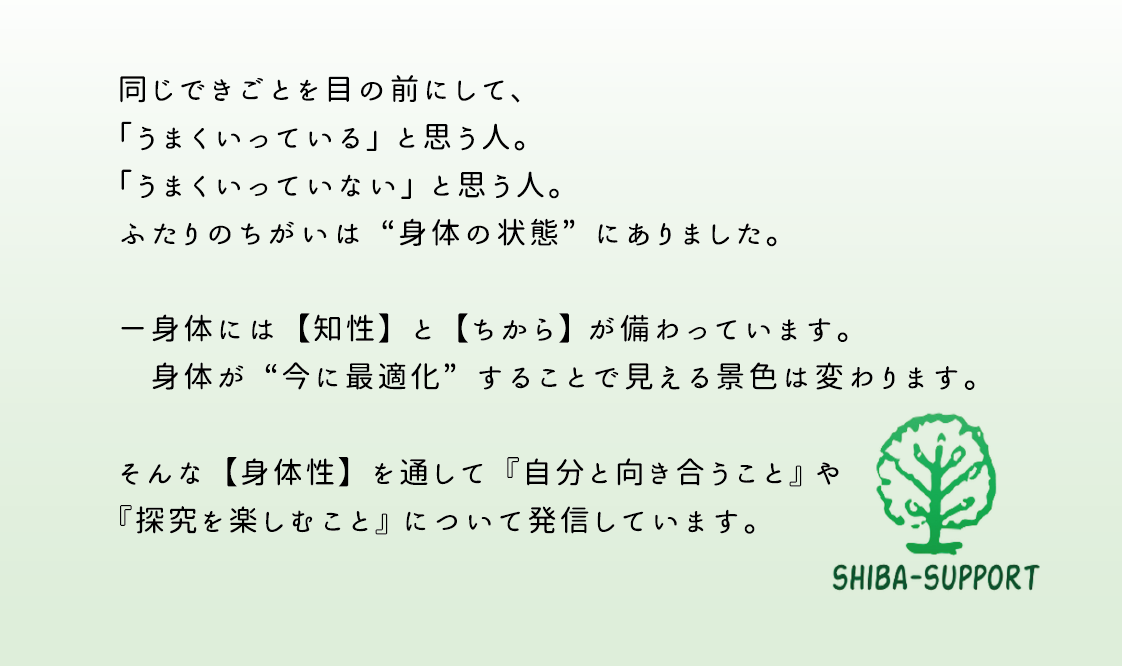桃太郎のおはなし
桃太郎はきびだんごをもって
鬼退治にでかけました。
その道中で出会った、
犬・さる・きじに
きびだんごをあげて
おともになってもらいました。
3人の仲間に支えられ、
桃太郎の心には少し余裕ができていました。
きじが桃太郎に尋ねます。
「どうして鬼退治に行くんだい?」
桃太郎は困ってしまいます。
悪者の鬼を倒せば、
村の人たちには尊敬されるし、
きっと謝礼だってもらえるはず。
でも自分がしたかったことは、
そういうことだっただろうか?
桃太郎は一人になって考えました。
そこは桃太郎が桃にはいって
流されてきた川の上流。
激しい川の流れが
頭のなかの雑念を
流してくれるようです。
桃太郎は素直な気持ちで
自分と向き合いました。
桃太郎だって一人の人間です。
おじいさんもおばあさんも
日中は家を空けていて、
桃太郎は一人で過ごす時間も長かったのです。
その寂しかった気持ちは、
いつしか鬼を打ち負かすことを
目標にすることでごまかされてしまいました。
それができたら、
おじいさんもおばあさんも村の人も
もっと自分を見て褒めてくれるはず。
そう思っていました。
でも、
ひとり、ふたりと仲間が増えていくなかで、
桃太郎の本当の望みは鬼退治ではないことに
気づかされていきます。
「みんな帰ろう。
おじいさんもおばあさんも心配してるよ。
島のくだものをお土産にして帰ろう!」
犬もさるもきじも、
突然帰るといいだした桃太郎に驚きますが、
なんだか嬉しそうです。
桃太郎たちは、
おじいさん、おばあさんと一緒に
お土産のくだものを食べながら、
旅の話をして楽しく過ごしました。
“どうして鬼たちは悪さをするんだろう?”
ふと桃太郎は思い立ち、
仲間を連れて再び鬼ヶ島へ向かいました。
鬼たちの話をきちんと聴くと、
鬼たちは、
村の人たちに外見だけで怖がられることが
寂しかったのだということがわかりました。
村にもどると、
桃太郎たちは、
そのことを村の人に
伝えるためちらしを配ったり、
直接お話をして伝えにいったり、
いろんな手を尽くしました。
桃太郎たちの行動の甲斐あって
村の人たちはすっかり鬼に心を開き、
鬼たちも村を守ってくれるようになりました。
桃太郎たちは
その活動を通して、
自分たちに“広報”の才能がある
ということに気づきます。
そして、
桃太郎たちには
どんどん仕事が舞い込んで、
感謝されることも増えました。
本来望んでいたことと、
行動していることが一致しているので
桃太郎はとても幸せです。
富や名声も手に入ったけれど、
もはやそれはおまけのようなものです。
鬼を退治して打ち負かせるよりも、
多くの人を幸せにし、
自分たちも豊かになることができたのです。
おしまい
———————
桃太郎が旅にでて
出会った仲間たちは、
【インナーチャイルド】の存在です。
その存在に気づき、
その存在にきびだんごという
優しさをあげて寄り添って
味方になってもらう。
いつの間にか、
成果をあげて評価をされることを
がむしゃらに目指すことがなくても、
なんだか満たされている自分を感じる。
人から賞賛されたり、
承認されるためではなく、
本質的にものごとを見てみようと
思えるようになる。
なぜかそこで自分でも気づいていなかった
ポテンシャルが生かせるようになる。
そしてなぜか、
人から賞賛されたり、
承認されるようになる。
もういらないと思ってたのに・・
と笑いながら、
素直に「ありがとう」と
受けとることができるようになる。
それを失ったら自分が保てない、
という執着がないから、
その豊かな循環は大きく広がって
周りの人たちをも幸せにすることができる。
もしも、
桃太郎がこの旅の途中で、
自分のなかの満たされなかった気持ちに
気づいてあげられなかったら、
そのまま鬼ヶ島に向かって、
コテンパンに鬼を退治して、
家に帰ってきただけだったら・・・
桃太郎自身も周りのみんなも今ほど
幸せだったでしょうか。
“欠乏感”【自分に向き合っていない状態】
からの行動と、
“満足感”【自分に向き合っている状態】
からの行動では、
その後にもたらされる成功にも
ちがいがあるようです。
“自分らしさ”へのプロセスを、
そんなふうにとらえてみても
面白いかもしれません^^
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^