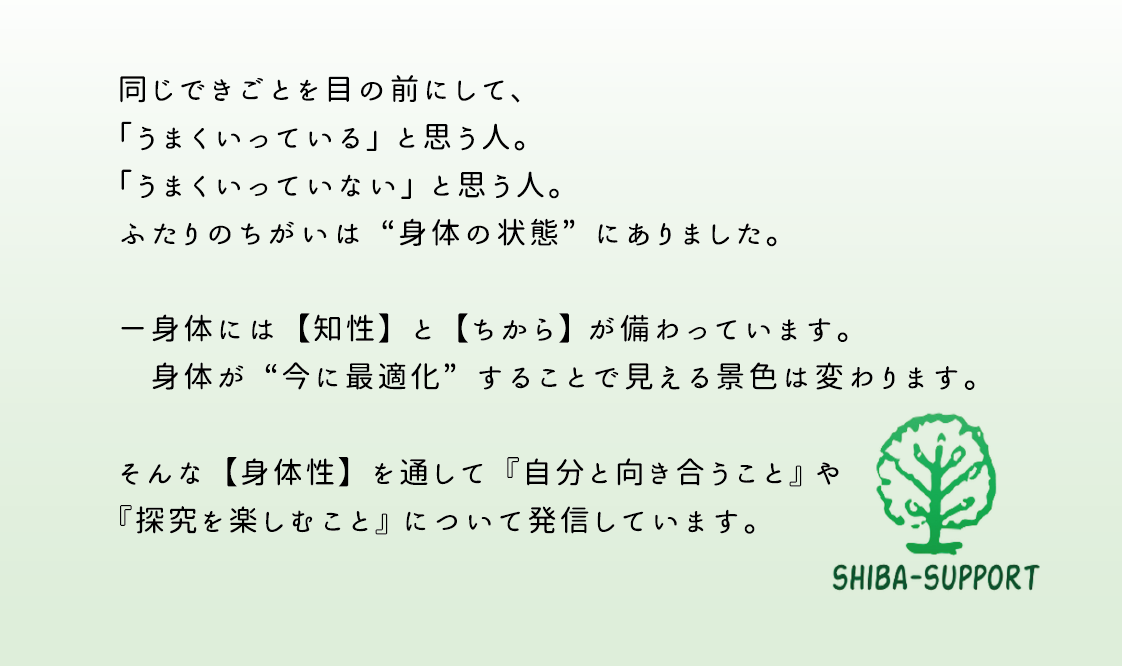『無理ゲー社会』の“自分らしさ”
前回の記事で、
【被害者意識】と【当事者意識】
について書いていたのですが、
ピッタリの題材の本に出会いました。
それがとても興味深かったので
ご紹介しますね^^
今年の夏、
『無理ゲー社会』という本が
出版されました。
“無理ゲー”とは、
攻略することが極めて難しいゲームのこと。
本書では、人生をゲームになぞらえて
その困難さを訴えています。
この本の存在を知ったとき、
私は、自分の思っている“自分らしさ”と、
本書が前提としている“自分らしさ”には
相違があるな、と感じました。
しかし、
本の帯だけの情報で、
その本一冊を理解したつもりになって
いろいろ考えるのもしのびないと思い
ちゃんと一冊読んでみました。
(※私の知識が乏しいがゆえに、
核がつかめていない可能性があります。
しかしこの記事で書いてみたかった部分には
影響がなさそうなのでこのまま続けますね^^;)
きらびやかな世界のなかで、「社会的・経済的に成功し、評判と性愛を獲得する」という困難なゲーム(無理ゲー)をたった一人で攻略しなければならない。
これが「自分らしく生きる」リベラルな社会のルールだ。
誰もが「知能と努力」によって成功できることになったことで、社会は「(知能の高い)上級国民」と「(知能の低い)下級国民」に分断されている。
上級国民:知識階級・評判社会において、「自分らしく生きる」という特権を享受できるひとたち
下級国民:「自分らしく生きるべきだ」という社会からの強い圧力を受けながら、それができないひとたち。
橘玲(たちばな あきら)著・小学館出版
“自分らしさ”についての定義は、
読む前の印象と同じく、
私が思っているものとはちがっていました。
私なりに“自分らしさ”を
発信してはいますが、
“自分らしさ”
=きらびやかな世界のなかで、
「社会的・経済的に成功し、評判と性愛を獲得する」だとは一度も思ったことがありません。
これって幾通りもある
“自分らしさ”のひとつですよね。
それがベストフィットな人もいるし、
そうでない人ももちろんいますよね。
たまたま発信力が強い人たちの
“自分らしさ”の共通項がそうだった、
という可能性はないのでしょうか。
“自分らしさ”
の探究のはてに上級と下級の分断が生じるなんて想像すらしたことがありません。
また、
“自分らしさ”を語る文脈で、
一度も自分と向き合うことについて
触れられていないことにも疑問が残りました。
そりゃ、
一人ひとりの色違いの
グラデーションも見つからないし、
“自分らしさ”が画一化されているのだから、
二分されるしかないのは当然かな…とも思いました。
(なにが正しい、
というわけではなく、
この定義ついては、
純粋に理解がおよびませんでした。。恥)
このままだと、
この定義がその結論を招いている、
ということも考えられますよね。
リベラルってなんでしたっけ・・・??
リベラル=自由主義、
というシンプルな理解でいくと、
そもそも
【知識階級・評判社会において】
という一見不自由なフレームは必要でしょうか?
私たち若者は、そもそも
【知識階級・評判社会において】
生きることを望んでいるんでしょうか?
「べつにそうなることを
望んでいるわけではないけど、
これからはそれが人に認められるらしい。
でも自分はそうなれない!
絶望だ!!」
…そういうことなんでしょうか?
むしろ、
このリベラル(?)な風潮の流れは、
そうした『人からの評価や承認』を
前提とした、しがらみのある環境で
人と比べて生きることから抜けだそう!
というところに潮目があるような気が
していましたが、ちがうんでしょうか…。
恥ずかしながら、
ここは本当に私の
無知がこの混乱を招いています。
リベラルについて、
もう少し理解を深める
という努力をしていきたいです。
でも、
この記事で書いてみたいことは
“自分らしさ”の定義について
ではありません。
———————
2020年1月に、
自民党の山田太郎参議院議員が
SNSで20-30代の若者に向けて
『あなたの不安を教えてください』
『私たちになにかできることはありますか』
とアンケートをとったところ、
「苦しまずに自殺する権利」として安楽死を
望む声が殺到した、という序章で本書は始まります。
ただでさえ不安の渦中にいる若者たちが
「自分らしく生きること」の圧力から
絶望の淵にさらされている、というのが
本書の主旨ですが、
後半きちんと救いもあるよ、
とフォローもされています。
ですが、
そのフォローも
「遺伝ですべてが決まるわけではないから
絶望する必要はない」といった論点であり、
その前提を覆すものではありませんでした。
この本を読んだ感想は‥‥
本当にまずいのは、
“自分らしさ”の定義の問題でも、
リベラル思考の考え方の問題でもなく、
この定義を目の前にして、
それを易々と受け入れ、
さらには絶望の淵にさらされている、
私たち若者世代の在りようかも、
と本気で感じました。
現役の若者のうちの一人として、
“絶望”なんて最後にしたらいいじゃない。
という気持ちがあるのが正直なところです。
序章の段階で
「おーい!絶望するのはちょっと待って!」
と、少し気持ちがざわつきました。
「夢を持たないこと」ですら、
“自分らしさ”だよ、といってあげれば
絶望の淵にさらされた人の半分は
もどってきてくれそうですが…。
本書の前提では、
それは許してくれなさそうですね。
だからといって、
わざわざこの定義の波に溺れていくことは
それこそが『被害者意識』であり、
私たちが圧力を【圧力】たらしめている、
といっても過言ではないように思います。
自分を非力化するような情報や概念を
シャットアウトすることも大切なことですよね。
本書では、
「理不尽で不都合な事実を
受けいれてしまったほうがいい」
とアドバイスしていますが、
世の中には幾通りもの事実があります。
たとえば本書には、
“女性の自立が加速すると、
男性の非モテが加速する”
という主張もありました。
これもひとつの事実なのかと
思います。
ジェンダーの質(男性性と女性性)の
視点からみた場合、
これは起こりうることです。
女性が収入で男性を選んでいる
というわけでなく(これは論外)、
あくまでもジェンダーの質から
考えたときにどうしてもそうなる傾向は強い、という意味です。
ですが、
それが自然な流れだとしても、
“絶望”する必要なんて一切ありません。
ちょっと視点を変えてみると…
日頃、
ガチガチに身体を固めている
高収入の男性より、
ある程度(平均以下の収入)でも
その範囲内で楽しむことができる男性は
リラックスも知っているので、
パートナーの満足度は高い、
という実際の統計もあるくらいです。
(これはジェンダーの質でいう
《女性性》が強い男性の例ですね^^)
こうした事実もあるなかで、
どうしてあえて不都合なものを
受けいれるのか?
という視点をもってみても面白いですよね。
どちらがいい悪い、
ということではなくて
心地いいと思う情報を採用して、
望むほうに自分を変えていけばいい。
快か不快か。
どちらにフォーカスするかで
起こる出来事は確実に
変わってきます。
情報が溢れかえる今、
情報とのバウンダリー(心の境界線)
をしっかりとひいて、
我ごととしないことも穏やかに生きていくために必要なスキルですよね。
ついつい自戒の気持ちも込めているので
熱くなってしまいましたが、
この問題の本質について、
私なりの解決策をお伝えしたいと思います。
【被害者意識】に陥ってしまうとき、
つまりは、
自分への“愛”がもてていない、
自分を諦めてしまっている状態です。
そりゃそうです。
先の見えないこの状況のなかで、
日々をこなしていくので精いっぱい。
こんなときに、
自分への“愛”をもつなんて
エネルギーのムダ遣いとも思えますよね。
でも・・・!
もしかしたら、なにか変化があるかもよ、
という軽い気持ちでお誘いしたいのは
“身体の細胞たちとちょっと仲良くなってみる♡”という試みです^^
“細胞たち”って、
こうじゃなくて・・・
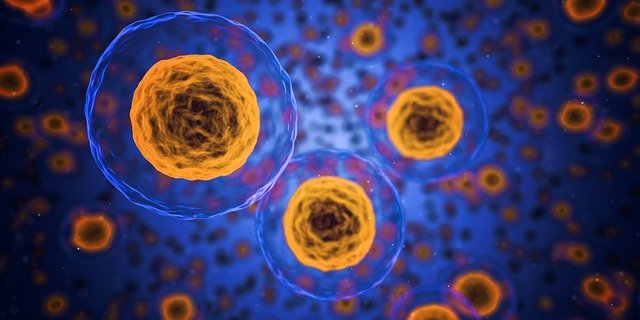
こんな感じです^^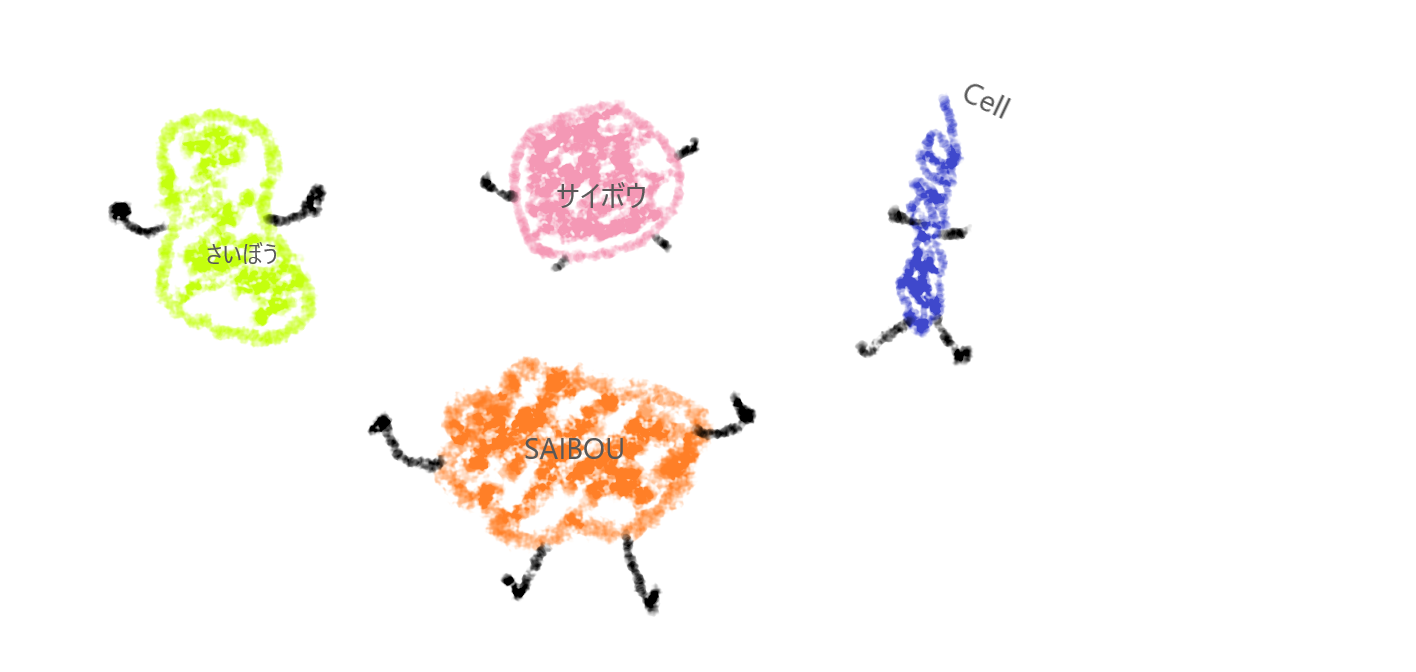 “自分を大切にする”とか
“自分を大切にする”とか
“自分を愛してみる”って
なんだか口幅ったいし、
めんどくさそうな感じがありますよね。
でも、
こまかいことはどうでもいいから、
“こんな感じの同志たちが
自分のなかにはたくさんいるんだな~”
っていう想像というか妄想するだけでも
ちょっと面白いかもしれません^^
私は探究と称して、
細胞たちと日々実験を繰り返しています(笑)
この提案はふざけているわけでも
なんでもなくて、
ただ自分を知ろうとしてみる、
というきっかけの一助になればと思っての提案です。
身体と思考をゆったりと柔軟にして、
“あ~そういうこともあるよね。
じゃぁこうしてみたらどうだろう?”
と我が道をいくことができれば、
きっと人生はそれほど苦しいものでは
なくなるのではないかと思います^^
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^