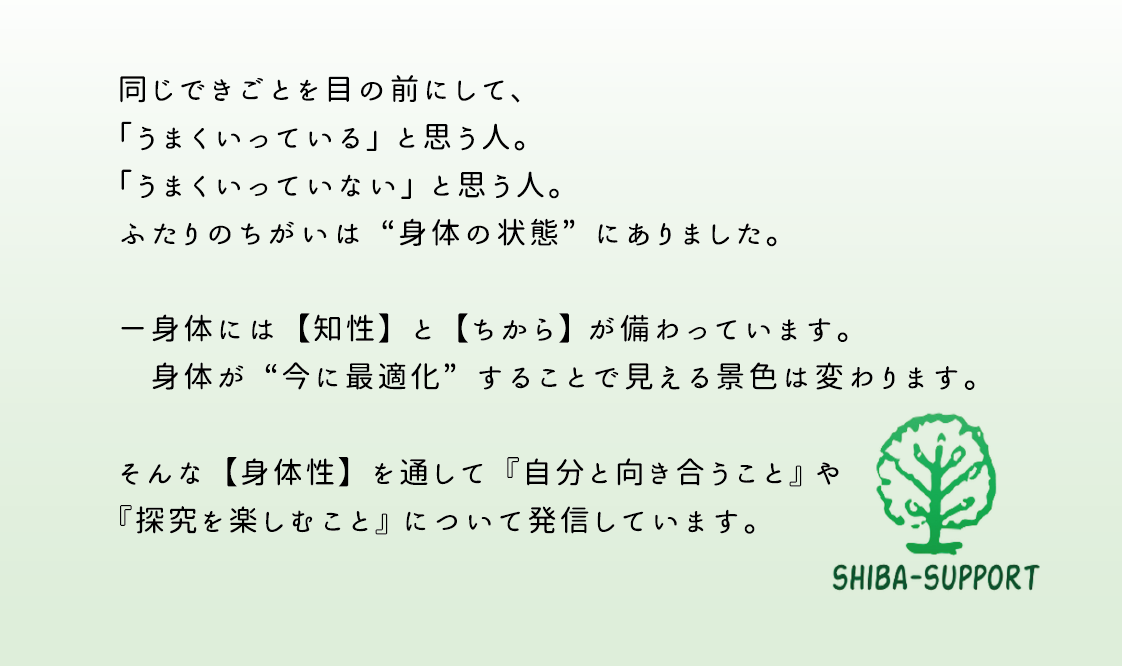-Contents-
これまでの【人体観】を覆し反響を呼んだNHK特番
こちらの記事で、
私たち一人ひとりが
自分らしく生きることが
世界に調和をもたらすのかも
しれない、ということをお話しました。
そのときに、
私たちの“自分らしい”の
ポジションをExcelのセルとして
表現しましたが、Cell(小部屋)には
“細胞”という意味もあります。
私たちの社会や組織が
少しずつ支配的なピラミッド構造を抜けて、
横ならびのフラット構造へ変わろうとしています。
その変化は医学の世界でも同じく
『人体観』の変化として現れています。
2017~2018年にかけてNHKスペシャルで、
【人体 神秘の巨大ネットワーク】
という特番が放送されました。
脳を頂点とした
ピラミッド型の人体観が覆され、
臓器たちがメッセージを送り合うという、
ネットワーク型の人体観が登場し、
大きな反響を呼びました。
それまでの医学の常識では、
脳が“司令塔”として、
すべての臓器をコントロールし、
それぞれの臓器たちはメカニカルに動き、
脳に支配されているとされていたのが、
なんと臓器たち自らのつぶやきと
受容により自己調律を図っていたという
事実が次々と発見されていったのです。
ふだんNHKの番組はあまり見ない私ですが、
この頃すでに
“身体って思っているよりずっと
すごいんじゃないか‥?
そしてそれは脳だけによるものではなく、
臓器というか細胞ひとつひとつにすら
その可能性が見いだせるのでは…?”
という気持ちが生まれはじめていたので、
この番組を見かけたときには食い入るように
見ていました(笑)
そして、2019年。
その番組ディレクターが、
シリーズを一冊にまとめた本が出版されました。
そのタイトルは、
『人体 神秘の巨大ネットワーク
臓器たちは語り合う』
しばらく本からの引用が続きますが、
番組全体の主旨である“ネットワーク感”
が実感できる部分を抜粋していますので
軽い気持ちで読んでみてください^^
まず、脳が人体を支配しているというイメージは、どこから来たのか?一つには、神経系の存在があります。人間は全身に張り巡らされた感覚神経で情報を脳に集め、運動神経で脳から指令を伝えて身体を動かしてします。まさに、脳が全身を支配している構図です。そしてもうひとつ、ホルモンの仕組みも、脳を中心とする人体観の大きな柱となっていました。脳の中心付近にある「視床下部」という部分は、いわばホルモンの“大元締め”ともいえる重要な部分です。
1980年代に、ANPと呼ばれるペプチド(ホルモンの一種)が、脳の指令ではなく、心臓が独自にだしているものだった、という発見がされたことで医学の世界にパラダイムシフトが起こりました。
ただのポンプだと思っていた心臓がホルモンを出していたのか!という当時の驚きは、なんとなくわかる気がします。まさにここから、「あらゆる臓器がメッセージを出す」という時代へ急速な展開が始まったと言えるでしょう。
メッセージ物質とは、正式名称ではなく、体内のネットワークのなかで臓器から臓器へ、細胞から細胞へと情報を伝えているホルモンをはじめとした物質全般のことです。
血管には、栄養や酸素を全身に運び、老廃物を回収する「輸送路」の役目がありますが、それと同時に「情報回線」としての役目も担っていたのです。血液を通して運ばれるメッセージ物質は、ほぼすべての細胞に行き渡るようになっています。
実際には、メッセージ物質は指令というよりも『つぶやき』と考えたほうがより現実に近いような気がします。心臓は誰かに命令しようというよりも、自分の状態をつぶやいているだけ。それが血液に乗って全身に広がっていくと、腎臓や血管がその声に応えて、行動を起こしている。そんなふうに見たほうがピッタリくるのです。これは、メッセージ物質全般にあてはまる特徴だと言えます。
細胞が、あるメッセージ物質を受けとるためには、そのメッセージ物質を受け取る専用の受容体が必要で、もし細胞が受容体を持っていなければ、メッセージ物質は素通りし、その細胞には何の影響も与えません。受容体は、受け取る側の細胞が、いわば“わざわざ”作るものです。受け取る側の細胞が、積極的にメッセージを“聞こうとしなければ”聞こえてこない仕組みなのです。
腎臓は体内の酸素不足を監視する「見張り番」として働いています。そして緊急の際にはエポを大量に出すことで赤血球の増産を促し、全身に酸素が行き渡る状態に引き戻す、という非常に重要な仕事をしているのです。これは、脳から指令を受けてやっているわけではありません。腎臓と骨髄が連携して、独自の判断でやっている仕事です。
臓器移植をすると拒絶反応が起きると言いますが、攻撃するのは、外敵と判断した免疫細胞だけで、他の臓器たちは、新しく来てくれた仲間を分け隔てなく迎え入れるのです。それにしても、世界の人類や国や民族で言語の壁があるのに、臓器たちは共通の言語で話しているとは、面白いことです。
脂肪組織がレプチンを出す量を調節することで、食欲をコントロールし、体重を安定させていることがわかったのです。ぽっこりお腹に詰まったあの脂肪が、人体の司令塔であるはずの脳に対して、指令を出しているという事実に世界が驚きました。
実は、肥満になると脂肪細胞がこの危険信号を過剰にまき散らすようになることがわかってきました。こうしたウイルスや細菌の感染がないにもかかわらず、全身の免疫が過剰に活性化している状態は「慢性炎症」と呼ばれます。慢性炎症が起きるのは、局所ではなく、全身です。特に、血管の中で起きています。また、赤く腫れるほどのものではなく、より弱い炎症です。そのため、慢性炎症になっていたとしても、自分自身で気づくことはありません。しかし、慢性炎症の状態が長く続くと、恐ろしい事態を引き起こしていきます。動脈硬化・糖尿病・高血圧など、以前はそれぞれ違った原因があると考えられていた病気が、最近の研究では、どれも慢性炎症をきっかけとしている可能性が指摘されはじめています。
やっかいな慢性炎症を鎮めるために、海外では免疫を抑制する薬を使った治療も始まっていますが、副作用の懸念があります。もっと自然な方法はないものか?そこでいま期待されているのが「筋肉」がだすメッセージ物質を利用することです。筋肉は体重の40%を占める、人体最大の臓器です。少し前までは筋肉と言えば、身体を動かすだけのもので「臓器」というより「組織」と呼ばれることの方が多かったかもしれません。しかし、筋肉が、私たちの健康に役立つ何種類ものメッセージ物質を発信していることが明らかになり、「臓器」とよんだほうがいい存在であることが明確になってきました。筋肉から大量に出ていることがわかったのは、「IL6」という物質です。(ILはインターロイキンの略)。このメッセージ物質に「慢性炎症を抑える働き」があることわかってきました。
最後に注目してもらいたいポイントは、メッセージ物質が持つ意味を、人間の言葉と一対一に対応させるのは非常に難しい、ということです。メッセージ物質は「文脈で」意味が変わります。細胞同士の複雑なコミュニケーションツールとして、タイミングや量、他のメッセージ物質との組み合わせ、さらには受け取る側の状況などで、多様な意味を持ちます。
Twitterのつぶやきも、タイミングや周囲の状況次第で、受け取られ方はまちまちです。不特定多数による、ヨコのつながりのオープンなコミュニケーションにおいては、社会的な文脈によって発言の意味が解釈されます。一方、タテ社会の原理に基づく、古典的なホルモンには、誤解を許さない「指令」に近い性質があるため、言葉との対応が付けやすくなります。メッセージ物質発見の歴史で言うと、指令に近く、はっきりとした意味が認識できるものから先に見つかってきた、という見方もできそうです。
造血幹細胞は、血液中のすべての「血球」の元となる細胞です。「人体の7割の親」と言えるのです。どうやら、造血細胞が分裂していく過程で、細胞同士が互いにメッセージ物質(サイトカイン)を出し合って相談しているらしいのです。造血幹細胞はまず大動脈の周辺で生まれ、ほどなく肝臓に引っ越してきて、血液を作り続けます。そして、いよいよ出産が近づき、外に出るぞ、というころになると、いそいそと骨の中に移動してくることが知られています。どうして骨のなかがいちばん安全だとわかるのか?骨の中で、造血幹細胞を呼び寄せている細胞たちがいるのです。実は、骨髄の中にいる細胞たちが、造血幹細胞にとって居心地が良い環境を作っているのです。そこへ、血流に乗って造血幹細胞がやってくると『おっいいとこあるじゃん!』とニッチ(適切なすみか)を見つけて、すみ着くことになります。では、居心地が良い環境とは何かというと、「造血幹細胞が、造血幹細胞のままでいられる環境」のことです。
造血幹細胞は分裂を繰り返して増殖し、赤血球や白血球に分化していきますが、そのとき、分化せず造血幹細胞はのままで残ってくれる細胞がいないと、大変なことが起きます。骨の中の細胞たちが作るニッチに、造血幹細胞の分化を止めてくれる働きがあるのです。ニッチは、いわば「君は、君のままでいて」というメッセージを出し続けており、これを受け取った一部の造血幹細胞たちは分化せずにいてくれるのです。
体は「ネットワークのネットワーク」なのです。骨以外の臓器の中にも、ネットワークは存在しています。たとえば、腎臓の中には20種類以上の細胞が存在しますが、これらも互いにメッセージ物質を使って会話していることがわかってきています。そして、こうした臓器内部の細胞ネットワークは、直接、他の臓器とも連絡しています。つまり、臓器を国家に例えるなら、国と国に外交関係があるだけでなく、細胞という個人レベルでも直接、コミュニケーションしているということです、
人体の中では、臓器同士のネットワーク、細胞同士のネットワークが複雑に絡み合っていて、しかも整然と機能を続けている。いまの科学ではまだ全体像が見えない、神秘の巨大ネットワークが、人体なのです。
引用元:『人体 神秘の巨大ネットワーク 臓器たちは語り合う』 丸山 優二・著
専門用語が続きますが、
著者の方の“伝えたい気持ち”が
とても伝わってくる、
できるだけわかりやすい順番で
丁寧に飽きさせないように
ひとつずつ表現されているので
一気に読めてしまいます。
人体の世界観を味わうには
とっておきの一冊なので
気になられる方はぜひ^^
さて、
社会の構造がタテ⇒ヨコへ
移行しているのとともに、
2000年代から本格的に
人体観がタテ⇒ヨコの視点で研究され、
主流になりつつあるというのは
単なる偶然ではないように思います。
『ヨコ』の視点で見えてくるキーワードのひとつは“ネットワーク”です。
人体の仕組みを
ネットワークとしてみていくと、
この世界の仕組みも
マトリョーシカのようなもので
細胞間のネットワーク、
臓器間のネットワーク、
人と人のネットワーク、
家族間のネットワーク、
地域間のネットワーク、
職場間のネットワーク、
国同士のネットワーク、
世界中のネットワーク、
惑星間のネットワーク・・・
私たちが《つながり》で成り立っていることがよくわかります。
これまでは、
人体の世界でも、
臓器たちが脳の一方的な指令だけで動いていることが当然とされてきました。
しかし、
近年の研究から、
臓器たちがそれぞれにメッセージを送り合い、つながりあうことで生命が維持されていたことが明らかになってきました。
人体の世界でも気づきだされているように、
誰かの一方的な意図や教義から行動するのではなく、私たち一人ひとりの意志で動いていくことがこの世界の《つながり》の恩恵を最大限に生かすことにつながるように思います。
すべてのことの本質は“つながり”にある
人体を語る文脈のなかで、
その仕組みがとてもSNSに似ているのだ
という表現がありました。
細胞たちはつぶやきもするし、
リツイートして拡散もする。
ときには炎上もする。
私自身、
アプリケーションを開発する会社に
勤めていたことがありました。
そこで交わされるSEさんたちの会話を
聞いていると、たまに
“あれ?この人たちは哲学の話をしているん
だっけ?”
という錯覚におちいることがありました(笑)
これは、
“なんの話をしているのか
さっぱりわからない!”
という意味ではなくて、
ITやプログラミングが語られる文脈のなかには、哲学的なエッセンス、ときには宗教的なエッセンスがふくまれていたような気がしたのです。
人体とSNS、
ITと哲学・宗教、
一見すると両極にありそうな領域が
結局は同じところに帰結している、
というなんとも不思議な感じ…。
ソマティック(身体性)という領域も
まさしくそれを体現したような
包括性をもっています。
心理学・医学・倫理学・
システム論・宗教学・
スピリチュアリティ・哲学…
あらゆる領域に“心身統合”という
ハブをかませることで、
より世界というものが
わかりやすくなっていくようです。
身体の探究を深める研究家の方たちは、
もれなく宇宙の話をされます。
この本のなかでも、
やはり人体の仕組みは、
宇宙を彷彿とさせる示唆がある、
とその関係性に触れています。
仏教のなかでも、
とくに真言密教の教えは、
私たちの内側にも宇宙がある、
と説きます。
それくらい
私たちのこの身体というか生命というものが
奥深く深淵で、そしてシンプルであることの
証明であるように感じます。
よくやくブログの主旨にもどって
きた感があります(笑)
この記事の意図は、
身体の仕組みを詳しく理解しよう
というものではありません。
また宇宙観や宗教観を
押しつけようとしているわけでも
ありません。
近年明らかになっていている人体観に
触れてみていただくことで、
すべてのものはつながっている、
という安心感を感じてもらいたいということ。
私たちが今握りしめている
宗教観をはじめとした価値観を
ふっと手放しても、
ちゃんとつながるべきところに
つながっているから安心していいんだ、
ということがお伝えできればいいなと思っています。
あらゆるものを眺めてみたとき、
私たちが根っこで求めている
“つながり”というものが、
どのスケールでも厳然と存在しているということ。
あらためて、
実感してみると、
なんだか感慨深いものがあります^^
そして、
ただただ単純に
面白いですよね(笑)
今すこし、
この世界が狭いもの、
自分にはどうしようもないものだと
きゅうくつな気持ちになってしまっている方へ。
なんだか抽象的でぼんやりとした、
でもなんとなく視界が広がるような、
視点が変わるような・・・
そんなものをこの記事から受けとっていただけたら嬉しいです^^
【身体感覚】がもたらす、俯瞰して視る力
そして、
もうひとつお伝えしたいことは
『身体感覚』をトレーニングしていくことでのメリットです。
身体感覚を自然に捉えられる
ようになってくると、
ものごとをよりシンプルに
考えられるようになります。
思考ベースで考えることは
この人生を生き抜くには
とても大切なことですが、
ときにものごとを複雑にし、
問題を肥大化させてしまいます。
身体感覚ベースで捉えていけると、
問題を過少化、もしくは問題のない状態へ
昇華させていくことができます。
それは、
身体感覚をとらえ続けることが、
『メタ認知力』を高めてくれるためだと
考えられます。
『メタ認知力』とは
ちがう表現をすると
《俯瞰して視る力》とも
言えるかもしれません。
『メタ認知力』についても
また記事を書いてみたいと思います^^
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^