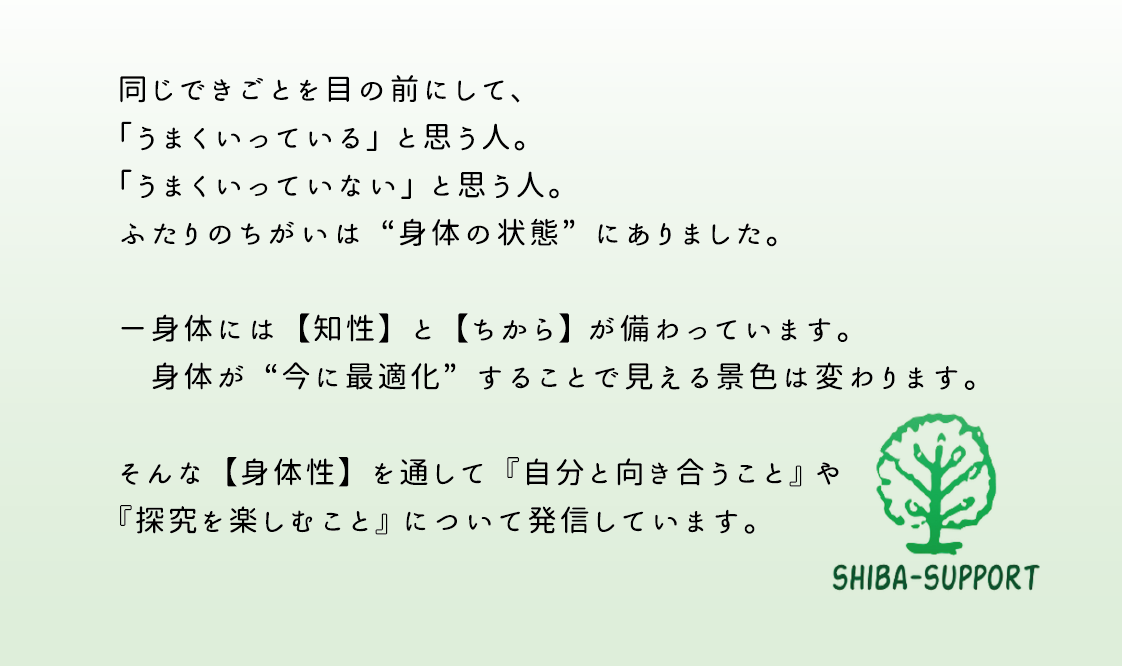-Contents-
「ネットワーク」という特性
こちらの記事に引き続きまして、
もう少しだけ、
『臓器たちは語り合う』より
引用していきますね。
免疫システムがうまくいく理由、さらに拡げて、人体そのものが、
ちょっとやそっとのことでは壊れない理由は何なのか?それをひと言で表すなら「ネットワークだから」です。人体のネットワークは「クモの巣」のようなもので、さまざまな臓器や細胞が、互いにメッセージ物質を出し合い、影響をおよぼし合っています。それが全体として一つのネットワークとなり、人体というシステムになっています。
メッセージ物質のほとんどが「引き戻す力」であり、一部に「導く力」と呼べるものがあると述べました。発生の過程は、この2種類のメッセージの“競演”です。
「こっちに伸びなさい」というメッセージは、まさに「導く力」。「あまり伸びたくない」は「引き戻す力」です。「引き戻す力」は、ネットワークを維持するために働き、「導く力」はネットワークを変化させるために働いています。
引用元:『人体 神秘の巨大ネットワーク 臓器たちは語り合う』 丸山 優二・著
引用が長くなってしまうので、
省略しているのですが、
ネットワークというものの特性として
《柔らかさ》が挙げられています。
私たちの身体の仕組みの根っこにある
ネットワーク特有の《柔らかさ(柔軟性)》
に生かされて『引き戻す力』と『導く力』
がまるで意志をもっているかのように
存在しています。
クモの巣をイメージしてみると、
なんとなくその柔らかさは
想像がつきませんでしょうか^^
それでいて、
たとえ一部が壊れたとしても
形を変えて全体を維持しようとする。
『引き戻す力』と『導く力』
その存在がたしかにあることを
ネットワークという特性が証明
してくれています。
【依存】と【自立】と《自律》
私たちが生きていくうえで、
その思考や行動、心の在り方が
【依存】に傾いていると、
生きづらくなっていくのは
なんとなく想像しやすいですよね。
自分という存在が、
他者ありきになってしまうので、
それは当たり前のことかもしれません。
だからといって、
その反対の【自立】に傾けばいいのか、
というとそうでもなさそうです。
「なんでも自分でやります!できます!」
「どんなことでも自分がやらなきゃ!」
「自分はこう思うから人は関係ない!」
こうした【自立】の在り方に傾くと、
私たちの身体が《一人では幸福になれない》
作りになっているので、
なんだか上手くいかない・・・
という状況になりやすいかもしれません。
【依存】も【自立】も
どちらにいっても不十分だなんて、
どうしたらいいんだ!とでも
言いたくなってしまいます。
たとえば仏教では、
最善な状態を表す言葉として
“中庸”というものがあります。
《自律》が目指すところはまさしく
ここであると感じます。
《自律》が目指すところは、
なにか特定の場所や状態ではありません。
《自律》とは、
“つねに自分の真ん中に在る”
もしくは
“つねに自分の真ん中に在ろうとする”
ということです。
“律する”と聞くと、
なんだかきゅうくつな、
コントロールめいたものを
感じてしまいますよね。
でも、
身体感覚を通した《自律》
をやっていくと、
とにかく楽になっていくんです。
それは、
身体感覚を通した《自律》は
【がっつきモード】ではなく
【受け取りモード】であるからなんです。
狩りに行く感覚と、
差しだした手で受けとる感覚、
どちらが楽に感じるでしょうか?
しかも、
後者で受けとるもののほうが
自分が本当に望んでいるもので
あったりするんです^^
身体の細胞がもっている、
『引き戻す力』と『導く力』は
まさに《自律》のための
パワフルな味方です。
私たちの身体の仕組みは、
高い【知性】と
頼りがいのある【パワー】
の両方を兼ね備えています。
(この【知性】と【パワー】
を生かした自己調律については、
こちらの記事を読んでみてくださいね^^)
身体がゆるまって、
柔らかくなっていくほどに、
思考には柔軟性が生まれます。
柔軟性とは、
『行ったり来たりが上手になる』
『自分の意志で行ったり来たりできる』
つまり、
常に自分の真ん中を中心に
考えたり行動することができるということ。
次第にその振れ幅は小さくなっていきます。
振り回されてしまいにくくなる、
ということです。
目の前で起こるできごとや
感情に翻弄されにくくなる、
ということです。
今までそこに対処するために
使っていたエネルギーを、
もっとちがうところに
使っていけるようになるんです。
一人ひとりがこうなっていくことができれば、世界はどうなっていくでしょう?
自分の機嫌を自分でとって、
与えられた“自分らしさ”を味わうことに
集中できる人が増えていけば・・・?
なんだか今とはちがう景色が
展開していくような気がしないでしょうか^^
神経システムのデザイン
ここで少し、
神経システムについて
触れてみたいと思います。
私たちが“リラックス”を感じるとき、
それには2種類のものがあります。
ひとつは、
“ひとりの時間”によってもたらされる
リラックス。
もうひとつは、
“人とのつながり”によってもたらされる
リラックス。
それぞれのリラックスで、
反応する神経系がちがうんですね。
“ひとりの時間”に反応する神経を
『背側迷走神経複合体』
“人とのつながり”に反応する神経を
『腹側迷走神経複合体』
とよびます。
神経の名前はまったくなんでも
いいのですが、
とにかく私たち(ほ乳類)の身体は、
一人では生きていけないようになっています。
ともにいる相手は、
家族、友人、パートナー、仲間…
など身近な存在だけでなく、
コンビニの店員さん、
タクシーの運転手さん、
病院の待合室で居合わせた人もそうです。
同じほ乳類である愛犬や愛猫ちゃんたちも
含みます^^
ときにはカウンセラーなどの
専門家を頼ってみることも大切なことですよね。
私たちの身体は《一人では幸福になれない》ようにデザインされています。
つまり、
《一人勝ちはできない》
ということですよね。
それなのに、
この世界の在り方は、
さまざまな場面で“勝つこと”
に執着させられるような構図が
あちこちに散らばっています。
自分たちの身体の仕組みと、
世界の仕組みが一致していないのだから、
多くの人たちにとって人生がネガティブなものになるのは当然のような気がしないでしょうか。
《自分を大切にする》
《自分を労わる》
《自分の好きなことをする》
今、こうしたことが
とても大切であるといわれるようになりました。
これは本当に大切なことで、
つまりは、
“自分の機嫌を人にとらせようと
しないことが大事”
とも表現できます。
それはわかっているけど、、
自分勝手になってしまわないか心配。。
と思ってしまう人はたくさんいます。
でも大丈夫です。
安心してくださいね。
私たちは【つながり】ありきで
存在しています。
自分のことを知っていくほどに、
本当の意味での“思いやり”や“愛”というものを人にも差しだそうと思えるようになっています^^
“深める”
という行為にはとても不思議な
性質があります。
《自分を理解する》を深めると、
対極にあるはずの
《他者を理解する》も深まっていきます。
《白を知る》を深めると、
《黒を知る》も深まっていきます。
《女を理解する》を深めると、
《男を理解する》も深まっていきます。
これは、
まさしくこの世界が“つながっている”
ということのなによりもの証拠ではないかと思います。
“生き物”としての自分を知ると癒される
意外なことですが、
こんなふうに“生き物”としての
自分たちのことを知ると、
少し癒されるものがありませんか?
みんなでワイワイするのも楽しいけど、
ふと一人になりたいこともある。
一人でいることが好きだけど、
たまにはみんなで楽しく過ごしたい。
生物学的にみると、
どっちも正解で、
どっちも不可欠なものです。
つねに人とつながりっぱなしでは
疲れてしまう。
でも
根っこではちゃんとつながりを希求している。
ただシンプルに、
そういうふうにできているんです^^
そしてもうひとつ
私たちは、
例外なくトラウマだらけです。
カウンセリングを受けたり、
人になにか相談をするとき、
“自分にはなんらかの問題がある”
ということが前提になりがちです。
ですが、
神経システム的にみたときに、
私たちは傷だらけでトラウマだらけで
当然という見解がでてきます。
そう思うと・・・
なんだかふっと力の抜けるものが
ありますよね^^
この記事では、
あえて対極にあたる言葉を散りばめて、
そこに【つながり】を感じていただけるように構成してみました。
“愛”とか“思いやり”が
わざわざ言葉として表現されるのは、
宗教やスピリチュアリティの領域ですが、
こうしていろんな視点でみてみると、
そういったものはどの領域にも存在していることがよく分かります。
この世界は、
ちゃんと温かい方向にデザインされている、
と言っても過言ではないように思います^^
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^