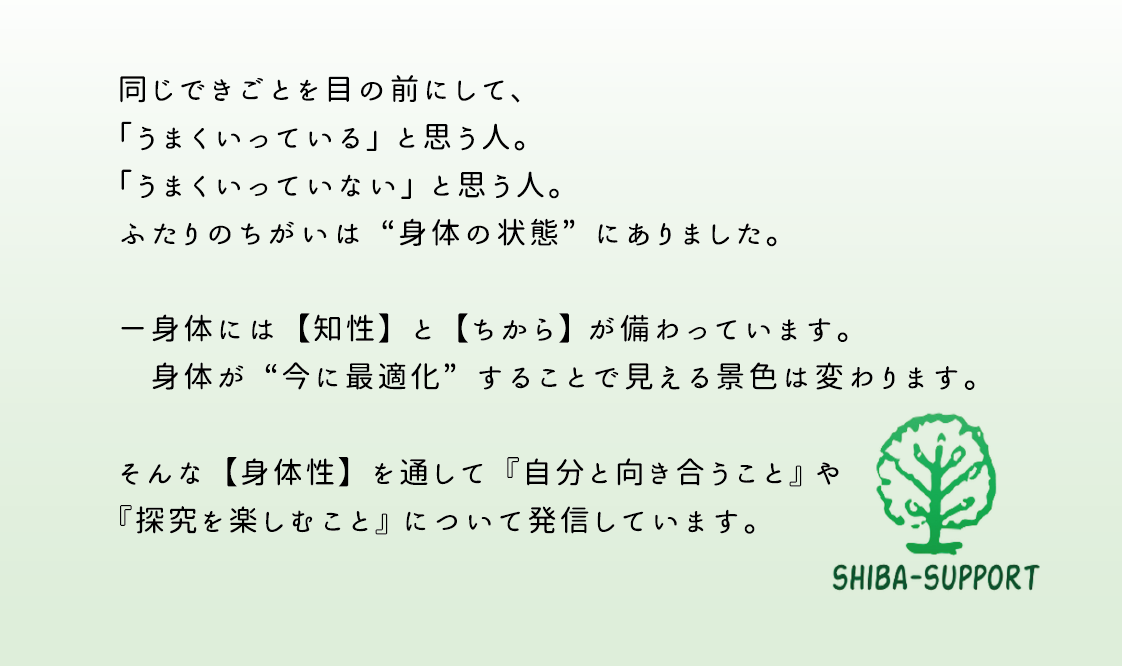-Contents-
はじめは「動的瞑想」から^^
「僕があなたの身体の細胞だったら
嫌になる。すぐに我慢するし、
褒められても受け取らないし、
もうこの人のために頑張っても
甲斐がないから働くのやめようと思うよ。」
ーはじめにの記事で少し触れたように、
漢方を処方してくれる中国薬膳の先生に
言われたこの一言がきっかけで
私の人生は大きく変わりました。
まずなにからしたらいいのか
わからなかった私は、
この記事でお話していたように
“自分が感じていること”を
知ろうとすることからはじめました。
そして大切にしていたのは
『動的瞑想』の習慣です。
“瞑想”というと、
あぐらの姿勢で、
目を瞑って、
呼吸に意識を向けて…
“無”になる、
というイメージではないでしょうか。
そういった
身体を動かさない瞑想を
「静的瞑想」と言います。
その逆で、
身体を動かすことで瞑想状態に至るものを
「動的瞑想」と言います。
たとえば、
合気道・ヨガ・ウォーキングなど
わかりやすいものから、
掃除や洗濯などの家事、
読書やメイクも
実は「動的瞑想」だったりします。
瞑想がいいよ、
と聞いてやってみたものの、
いまいち良さがわからず辞めた
という人も多いものです。
忙しい日々が続いていたり、
頭が情報で疲弊していたり、
思考が走り続けていたりすると、
“無”でいることに浸りきれません。
また
過去に強いトラウマがあったりすると、
「静的瞑想」がうまく機能しないどころか
危険すら伴います。
なので最初は
「動的瞑想」がおすすめです^^
私自身、
身体のことをないがしろに
していたかというというと
そうでもなく、
お風呂あがりのストレッチは
10年以上続けているし、
平熱も37℃近くあるし、風邪もひきにくい。
それほど身体を雑にあつかっているつもりは
ありませんでした。
しかし、
それはあくまでも
表面上だけのことでした。
自分と向き合う、
という意識で、
自分を理解してみよう、
労わってあげよう、
という気持ちでいたことは
ありませんでした。
————————————–
《伸ばす》のではなく、
《伸びていることを感じてみる》
《伸ばす》というのは、
顕在意識的なMind主体のアプローチです。
《伸びていることを感じてみる》
というのは、
潜在意識的なBody主体のアプローチです。
————————————–
ちょっとイメージしながら、
やってみてくださいね。
首を優しく右に傾けてください。
まずは、
首の左側を《伸ばそう》
という意識。
そして今度は、
首の左側が《伸びるのを感じてみよう》
という意識。
どうでしょうか?
なんだか感じることや
力み方が変わってきませんか^^
“理解してみよう”という気持ち
信仰中心のマインドが
自分中心のマインドに変化するとともに
身体が変わっていることを感じるできごと
がありました。
小さい頃、クラシックバレエを
習っていました。
大人になってからも運動不足解消のため
週に一度バレエのレッスンを受けています。
今では
バレエの時間が
大切な『動的瞑想』の時間です^^
私は、
家族のために、
宗教のために、
会社のために・・
と外側のものを大切にして生きていたので、
外側のものにしがみつくための力みで
全身がこわばっていました。
自分を非力化しながら
外側のものにしがみついていたので、
ただ立つだけでも力んでしまっていたんですね。
バレエのレッスンのたびに
先生から、
「あなたの身体の動きは、
リモコンを取る動きひとつでも
10㎏の米俵をもっているみたい。
もうクセになっているから、
先生には直せない。」
とよく指摘をうけていました。
意味もわからず、ただ自分が悔しくて、
とても信頼している先生だったので、
先生の言葉の真意をしりたいと何度も
思いました。
でも言葉で直接質問するのは
なにかちがうと感じたので、
まずは自分で観察してみることにしました。
たしかに私の身体は、
自力で立つと力みすぎていて、
先生にも直せない。
だけど、先生にゆだねようと
すると脱力しきってしまって
立てなくなってしまう始末でした。
物理的に身体になにか
不自由がある、
ということではなく、
身体があるべき自然な位置に
調整してもらうと、
こんな状態になってしまうのです。
0か100の状態です。
まるで
自分の中心に軸がないために、
このような身体の動きになっている
のではないか?
と感じるほどでした。
まさしく
その通りでした。
ところが、
少しずつ身体となかよくなっていくことに
取り組んでいくことで、
私にとっての快・不快、
もともとどんな人で
どんなことを考えていたか、
どんな過ごし方を望んでいたか、
どんな生き方を望んでいるか、
そんなことがわかるようになって、
外側のもののためではなく、
自分のために生きることが
できるようになってきたとき、
身体にも変化があったのです。
先生にゆだねようとしても、
脱力しきることなく、
しっかりと立ち続けることができました。
自分の中心に軸があることで、
ふっと力を抜いたときでも、
50の力できちんと立っていることが
できるようになったのです。
先生はびっくりされていました(笑)
わざわざ言葉にすることはしなくても、
先生は、
私の内面でなにか変化が起こっていたことに
気づかれていたようです。
このことを体感として
感じられたとき、
レッスン後の街の景色は
レッスン前よりずっとずっと
色鮮やかでした^^
もうスキップして
帰ろうかしら♡♡
と思えるような、
じわっと温かく、
でも軽やかな気持ちでした。
バレエのレッスンのときだけでなく、
自分でストレッチをするときにも
前屈したり開脚したりが楽になり、
可動域が広がっていたり、
肩こりや背中のこわばりが
やわらいでいたり、
朝起きたときに身体が軽く
すっきりしているのを実感できる
ようにもなりました。
最近では、
可動域の変化で、
自分の心理的ブロックの存在に
気づけるようになってきました(笑)
Body(身体)と Mind(思考)がつながって
いることを体感しました。
Body(身体)を大切にしたり、
伝えてくれることを受け容れようとしてみる。
そうすることで少しずつ
Mind(思考)も変化する。
そして、それが再び Body(身体)に
目に見える変化として表れる。
この経験は
一生の財産となりました。
意識せずにストレッチしていたときは
完全に分離していた
Mind(思考)とBody(身体)に一体感
が生まれました。
“自分を知ること”
“自分を労わること”
“自分を大切にすること”
“自分に行動させてあげること”
身体を通して自分と向き合い、
身体がそれに応えてくれた。
身体の細胞たちに
『あなた達のことをもっと
知りたいと思ってる。』
という好意的な気持ちや
『いつもありがとうね^^』
という労いの気持ちがちゃんと伝わって、
私が想像していた以上の変化を
もたらしてくれました。
そこに
抑圧やコントロールはまったくなく、
ただそういう気持ちを向けていました。
これって
人との関係を築くときに
よく似ていませんか?
単純に
習慣で、とか
美容のために、ということでなく、
心を開いて身体に意識を向けていく。
ただ単に
同僚だから、とか
ご近所さんだから、ということではなく、
心を開いて相手に意識を向けていく。
そしたら
二人のあいだに少しずつ信頼が
生まれてくることは簡単にイメージできますよね^^
自然治癒力、とはよく聞きますが、
本当に身体というものは、
信頼してあげるだけで
ベストな状態をもたらしてくれます。
単純にフィジカルなことだけでなく、
思考的なところでも。
そうすると
周りの環境や状況も変わってくるのは
自然なことですよね。
なにひとつ
難しいことはありません。
いつもしているスポーツや家事、
メイクや読書などの《動的瞑想》を、
身体に対する好意的な気持ちや
労わりの気持ちをもってやってみて
くださいね^^
メイクブラシが頬に触れることを
感じてみる、
本のページをめくる指の感覚を
感じてみる・・・
いろいろ試してみてください。
まずやってみる。
この一歩がとてつもない実りを
もたらしてくれるかもしれません^^
【自己信頼力】があると頑張らなくていい
ここで何が培われているのかというと
【自己信頼力】です。
心理学でも
『自己肯定感』や
『自己受容感』という言葉がありますが、
この一体感を表現するには
【自己信頼力】という言葉が一番しっくりきます。
なんだか自分自身が頼もしいというか、
力づよい感覚ですね。
きっと水面下では、
私のなかの
“男性性”と“女性性”のバランスがとれる、
ということが起こっていたのでは
ないかと思います。
(こうしたジェンダーの質の概念についても
記事にしてみました^^)
私はもともと
少し男性性が強めなタイプなので
「頑張らなくていいんだよ」
という言葉をかけられると、
戸惑ってしまうところがありました。
頑張ることや努力することでなにかを得た、
という経験の積み重ねもあっただろうし、
なにか役割を果たさなくては、
という使命感のようなものもありました。
だから、
いろんなことをこなしていくのに、
力んで、踏んばって、
「えいやっ!」とやってみる。
寝ることも大好きで
基本的にだらだらしていたいのに、
そうした時間に罪悪感をもってしまう。
そういうときの身体の感覚って
やっぱりちょっと重たいというか
ぐっと踏んばる感じがありますよね。
自分を信頼していないから
(=足りない、が前提)
「頑張らなきゃ」となっていた。
自分を信頼している状態だと
(=ある、が前提)
「頑張らなくていい」になる。
かつて努力や根性であったものが
「楽しむこと」になっていく。
こちらの記事でお話していたように、
Mind(思考)とBody(身体)の一体感が
Spirit(本質的な自分)を体現してくれる
ようになるからですね^^
この一体感はいろんなメリットを
もたらしてくれるのですが、
私の場合は、
【自己信頼力】の高まりとともに、
メリハリがはっきりしてきました。
やらない!と決めた日は
びっくりするほど寝ます。
やらないときは
トコトンやりません。
根っこに自分への信頼があるから、
頑張ることでなにかを保つ必要もないし、
ちゃんと休んでも私が失うものは何もない、
という発想に変わっていくんですね^^
もちろん今でも
「頑張らなきゃ」
がでてきてしまうこともあります。
でもそのたびに、
“あら~なんか足りないって
思っちゃってるのね。
なにが足りないと思ってるんだろう?”
って立ち止まってみます。
立ち止まることが時間の無駄のように
思えるけど、このあとの飛躍を考えると
こういうときは立ち止まってみるのも
おすすめです。
(※こうした自身とのパートナーシップの
感覚をつかむのに、パーツ心理学という
概念をしっていると、とてもスムーズです。
またご紹介しますね!
⇒記事を書きました)
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^