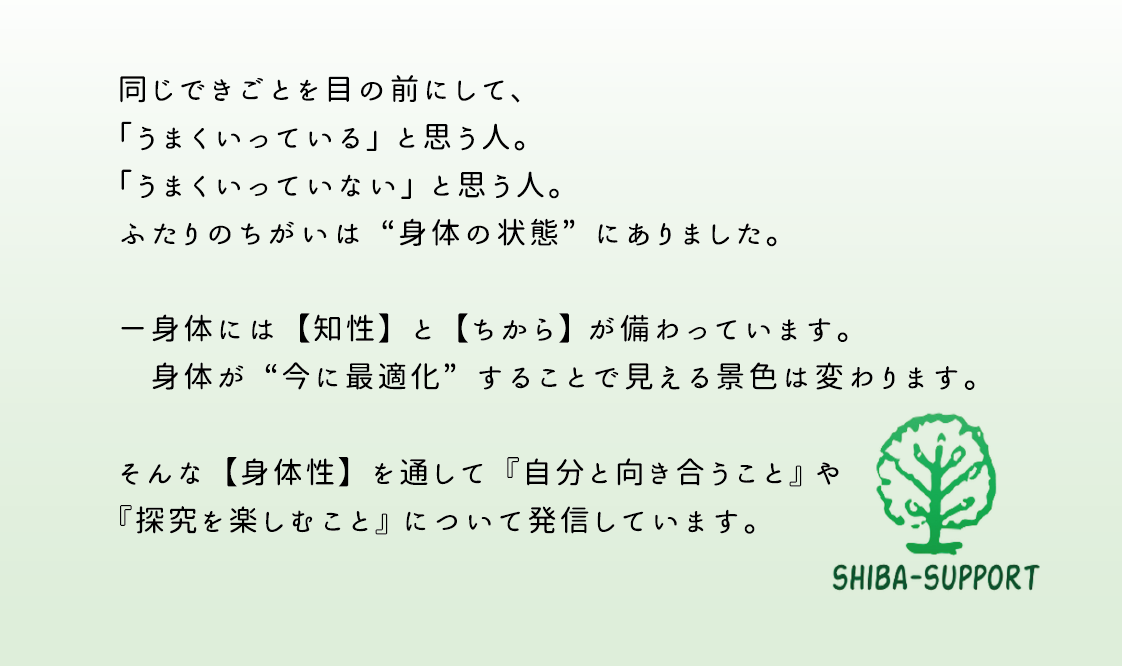-Contents-
思考(左脳的)と身体感覚(右脳的)
前回の記事で、
活動のコンセプトを少し広げて
いきます、ということを書きました。
ともなって、
このブログのタイトルも
“ソマティック(身体性)な探究で
人生を深く味わうためのブログ”
に変更しました^^
「ーはじめに」のページも
あらためて書き添えてみたので
よろしければお読みください。
———-
『ソマティック(身体性)』について、
言葉にして表現することは
難しいなぁとあらためて感じています。
とても感覚的なことなので、
当然といえば当然なのですが、
だからこそ、
一人ひとりの“探究”が
味わい深いものになるのだな、と
その可能性をあたらめて感じる
きっかけにもなっています^^
今回の記事では、
ソマティック(身体性)を
深めていくために、
✓【How?(方法と材料)】
✓【培われるもの】
✓【もたらされるもの】
✓【努力の必要性】
✓【心理学的なアプローチ】
の5つの観点から、
“思考(左脳的)”とのちがいについて
書いてみたいと思います。
さきに書き添えておきたいのは、
思考(左脳的)は不要で
身体感覚(右脳的)だけが必要だ、
ということではなく、
やっぱり思考の力も大切です、
ということです。
これまで抑圧しがちだった
身体感覚のちからを解放して
バランスよくしていきたいですね^^
身体感覚によって
もらたされた“気づき”によって
次の一歩を踏みだすとき、
思考のちからがもれなく発揮されます。
どちらも欠かせないもので、
身体感覚⇒思考、
という順番が大切なんですね^^
思考だけで進んでしまうと、
それは本質的な望みからずれたところで
目標設定をしてしまうようなものなので
そのプロセスがしんどくなってしまうのは
なんとなく想像ができますよね。
身体感覚に耳を傾ければ、
本質的な望みとのずれも小さくなるので
そのプロセスも“しんどさ”から“楽しさ”へ
変わっていきます^^
———-
私たちは、
日頃から身体感覚を
抑圧している傾向にあります。
それには、
こんな目的があります。
✓ “感じないようにする”ことで
かつて負った傷や苦痛を
シャットアウトしている。
✓ “感じないようにする”ことで
本当の望みにフタをして、
今ある体裁や環境を維持しようとしている。
この目的たちをみると、
このままにしておいたほうが
人生はうまくいくのでは・・・?
なんて思いますよね(笑)
でも、
本質的な私たち、
つまり“魂”というものは、
そんな誤魔化しがいつまでも通用するほど薄っぺらいものではありません。
あるときふと、
そのタイミングがきて、
“停滞感”や“違和感”・“虚無感”という形でサインをだしてきてくれるかもしれません。
こうしたサインに
【思考】で対処しようとすると、
「なかったことにしよう」とか
「あ、なんか勘違いかも」
という判断をしてしまいがちです。
人や環境のせいにして、
向き合うことなく過ごすこともあるかもしれません。
でもそれはとてももったいない。
このサインたちは、
“人生のステージを
ちょっと進めてみませんか?”
という示唆であることがほとんどです。
そんなとき、
身体感覚を解放していくことが
成長や成熟をもたらしてくれるんです。
そしてその秘訣は
“楽になること。
できるだけ努力しないこと。”
私たちは、
“楽になること”が
成長につながるなんて思えないような
教育を受けてきていますよね。
でも、
ソマティック(身体性)の探究によって
もたらされるものは、
“自分が楽になること”が
私たちにとって
大切な成熟のプロセスであることを
教えてくれます。
いよいよ意味がわからなくなってきましたね(笑)
このブログは、
「あたま」ではなく「おなか」で
読んでいただく感じがちょうどいいかも
しれません^^
少しでも、
ソマティック(身体性)を分解して、
わかりやすく言葉にしていければと
思っています。
How?|【コントロール】と【最適化】
ひと言で表現してしまうと、
思考のやり方は【コントロールする】、
身体感覚のやり方は【今に最適化する】、
であると言えます。
そして、
材料となるものは、
それぞれこんなものがあります。
《思考》
✓ 過去のデータ
✓ 愛されるための生存戦略
《身体感覚》
✓ リソース(心地よさ)
✓ 感情・感覚
●【思考】は、
過去のデータや生存戦略を用いて、
“コントロール”しようとします。
いろんな大きさの鍋と
多種多様な野菜やお肉、調味料を準備します。
使い古したたくさんのレシピのなかから
今回の場合はどのレシピが有効なのか
検証や分析をします。
それぞれの材料を間違いなくg単位で
下ごしらえしてレシピ通りに調理をし、
なんとかこの問題を切り抜けようとします。
⇒身体にはなんとなく“緊張感”があります。
●【身体感覚】は、
リソースや感情・感覚を用いて、
“今に最適化”しようとしてくれます。
お気に入りのほっとく鍋に、
ざっくり切った野菜と少しの調味料を
放り込んでおきます。
私たちがやることはこれだけ。
あとは“ちょうどいい塩梅になる”のを待ちましょう^^
⇒このとき身体からは“緊張感”が抜けていきます。
【思考】のやり方は、
過去に使い古したレシピがもとに
なっているので出来上がる料理も
《想定内》のものになっていきます。
【身体感覚】のやり方は、
勝手に“ちょうどいい塩梅に”
調理してくれるので、
出来上がる料理は《想定外》なものになることが少なくないのです。
【身体感覚】が、
自分の本当の望みや
未知のポテンシャルを教えてくれることが、
なんとなくイメージしやすくなるでしょうか^^
—————
ほとんどの哺乳類は、
“今に最適化するための能力”を
もっています。
これは生き物がもつ【身体感覚】によるものです。
もちろん、
私たち人間にも備わっている能力です。
でも、
人間はその能力を
生かしきれていません。
それは私たち人間が
【思考】する生き物だからです。
私たち人間は、
どれだけ小さなものであれ
怖かったことや不安だったこと、
弱さを突きつけられたことなどの経験を
身体の“緊張感や力み”として保存しています。
これが一般的に『トラウマ』
と呼ばれるものです。
こちらの記事でも
少し書いていたように、
『トラウマ』と聞くと、
幼少期の虐待やDV被害など
大きな被害経験を想像しがちですが、
実際にはほんの些細なできごとが
『トラウマ』となっている人もたくさんいます。
そして、
この『トラウマ』を抱えるのは
人間だけと言われています。
たとえば、
草原に生きるシマウマだって、
獰猛なライオンに追いかけられたり、
命の危険にさらされたり、
人間と同じように怖さや不安、弱さを
感じるような経験をしているのです。
でも、
『トラウマ』にはなりません。
ぎゅーっと身体を緊張させて
ライオンから逃げきる、
ライオンが去っていくのを
木陰から確認してから、
「ふーっ」と身体の緊張を抜ききって
仲間のもとにもどっていきます。
身体に“緊張感や力み”を残さないから、
『トラウマ』も抱えないのです。
シマウマをはじめとした
人間以外の動物たちは【思考】に
邪魔をされないから、
【身体感覚】のままに“緊張感”を
抜ききることができるんですね。
ところが人間はそうもいきません。
私たちが幼い子どもだった頃、
“お姉ちゃんだから我慢しよう”と、
良い子でいることを選んだり、
“本当は泣きわめきたい”
という気持ちをそっと胸の奥に閉じ込めて
その自分への秘密をずっと抱え続けます。
身体は「ふーっ」と力を抜ききって、
その体験を完了させていつでも“今”に
最適化していきたいと思っています。
でも、
【思考】のコントロールによって、
“緊張感や力み”を抱え続けることになるのですね。
お母さんや周りの大人たちに
“愛されるため”には【思考】のちからが
どうしても必要でした。
大人になってもそれは同じで、
人に認められ、愛されるために
やっぱり【思考】をフル稼働させています。
こうした
人間社会で生き抜くための【思考】が
『トラウマ』の原因であるとも言えるんです。
つまり、
私たち人間の身体は“今”を生きていないのです。
ぎゅっと力をいれた“あの瞬間”に
身体は最適化されたままなんです。
そして【思考】優位で生きる私たちは
今もずっと“あの瞬間”を積み重ねて
緊張し続けています。
ちょっとイメージしてみると、
なんだかしんどさを感じますよね。
だからこそ、
【思考】を鎮めることと【身体感覚】を意識することが大切なんですね^^
✓ “身体に意識を向けてみる”
✓ “身体を楽にしてあげようとしてみる”
こんなに簡単なことでいいんです^^
私たちがインターネットを使うとき、
ブラウザの調子が悪くなると
“キャッシュのクリア”を試しますよね。
蓄積されてきた余計なデータや
ほこりのようなものをワンクリックで
クリアしてくれる便利な機能です。
キャッシュをこまめにクリアしておくと、
ネットサーフィンもPC作業も
さくさく軽快♪ですよね^^
身体感覚も同じようなもので、
身体に意識を向けて
“ちょっとした力み”に気づいてあげるだけで
それらはクリアされていきます。
「あ、また呼吸がとまってた!ふーっ」
「あ、少し肩があがりがちかも?」
「猫背ぎみだから気をつけよ」
こんなことのひとつひとつも、
過去に蓄積された力みのクリアに
つながっています。
こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
これまで
“緊張を抱える”ために使われてきた
エネルギーが、今に最適化されることで
未来へのクリエイティビティにつながって
いくことがなんとなく見えてこないでしょうか^^
なぜ、
その人の本当の望みが見えてくるのか?
ポテンシャルが発揮されやすくなるのか?
それは、
「身体が今を生きられるようになるから」
ということがひとつの理由なんですね。
培われるもの|【愛される能力】と【愛する能力】
ソマティック(身体性)と
“愛”の関係性についてお話してみますね。
思考の方法が、
【愛されるための能力】を培うとしたら、
身体感覚の方法は、
【愛するための能力】を培うと表現できます。
この世界では、
“愛されること”に
最大の関心が向けられています。
“愛されたい”とは、
異性から“愛されたい”、
家族から“愛されたい”、
お金から“愛されたい”、
お客さんから“愛されたい”、
のようにあらゆる人間関係において
生まれる欲求です。
そして、
“愛される”ための
商品やサービスは売れますよね。
これは、
“愛されること”が最大の幸福である、
と思い込んでいることが原因です。
それは私たちが
赤ちゃんだったときに身につけた思い込みです。
これは自然なことですよね。
お母さんやお父さんはもちろん、
周りの大人たちに愛されなければ
赤ちゃんは生き抜くことができません。
“愛されるため”に
赤ちゃんだった頃の私たちは
さまざまな生存戦略を身につけました。
✓ とにかく聞き分けよく良い子でいようとする。
✓ わざといたずらをしてお母さんの気を引こうとする。
✓ “できること”を増やして褒めてもらおうとする。
✓ “できないこと”を増やしてかまってもらおうとする。
その戦略は赤ちゃんによってさまざまです。
こうした過去の生存戦略が
データとして思考にインプットされていきます。
そう、
思考にインプットされた成功法則は、
“愛されるため”の方法たちなんですね。
前述した、使い古したレシピたちです。
でも大人になった私たちは、
もう愛されなければ生きていけない
赤ちゃんではありません。
————
そんな大人の視点で“愛”について
もう一度振り返ってみたいと思います。
赤ちゃんの頃に身につけた
“愛されるため”の生存戦略には
いつしか限界が訪れます。
【愛されること】だけでは、
私たちが虚しさから解放されることは
ないことを知るからです。
【愛されるための能力】だけでなされる
自己実現には限界があることに気づかされるからです。
そんなタイミングが訪れたときが
成長のチャンスなのかもしれません。
【愛されること】から
【愛すること】へのシフトが、
成長と成熟をもたらしてくれます。
ソマティック(身体性)という視点は、
【愛されること】よりも
【愛すること】をやってみようと
思えたとき切り拓かれていきます。
【愛されるため】の方法から
【愛するため】の方法に変えようとすると、
恐怖心や不安の感覚が生まれることがあります。
それはこれまでの
慣れきった方法(コンフォートゾーン)から
抜けだすときに生じる痛みであり、
私たちの成長を阻もうとする無意識の
しわざです。
(無意識からすると私たちを安全なところで
守ってあげたいだけなのですが…^^;)
そこを抜けることができれば、
実は【愛されること】より
【愛すること】を選んだほうが楽で、
さらにその恩恵も大きいことが
腑に落ちるようになっていきます。
たとえば、
ビジネスの世界では、
どんなときも自分自身が
“Giver(与える人)”であるか
“Taker(奪う人)”であるかを
自覚しましょう、と言われますよね。
“Giver(与える人)”は
愛する能力に優れた人です。
“Taker(奪う人)”は
愛されることに熱心な人です。
ビジネスにおいて、
どちらが上手くいきやすいのかは
なんとなく想像できますよね^^
もちろん
“Giver(与える人)”です。
そして結果から表現すると、
“Giver(与える人)”は
愛する能力によって、
結果として【愛される】
という恩恵を受けることに
なっていきます。
————–
◆思考の“コントロール”により
【愛されること】ができるようになります。
でも【愛すること】との循環は生まれないので継続性はありません。
◆身体感覚の“最適化”により
【愛すること】ができるようになります。
【愛されること】との循環が生まれるので継続性がでてきます。
【愛すること】⇔【愛されること】
の循環が生まれるかどうかは、
この世界の原理原則のひとつである、
“出したものが返ってくる”という法則によります。
“愛”を奪うばかりでは、
なにも返ってこないのは当然ですよね。
“愛”を与えることによって、
“愛”が返ってくるのも当然のことですよね。
この世界はひとつの“つながり”です。
こうした原理原則が、
人間関係においてだけ、
ビジネスにおいてだけ、
“例外である”
ということはないんですね。
ビジネスだけでなく、
恋愛をはじめとした人間関係も
“愛すること”を先にしたほうが
上手くいくようです。
こうした、
“Giver(与える人)”と“Taker(奪う人)”
の文脈を早とちりしてしまうと、
“他者に愛を与えること
(人を愛すること)”
に走ってしまうそうになります。
それが【思考】のやり方なんですね。
【思考】はまず“愛されよう”とするので、
『自分から与えたら愛してもらえるのね』
という考え方をしてしまいます。
これが物事を停滞させる、
《期待》や《執着》にもつながっています。
【思考】のやり方は、
どちらかというと、
ウサギとカメのウサギさんです。
最速の方法だ!と思ってしたことが、
その《期待》や《執着》によって思い通りにいかないことも少なくありません。
カメさんのように
力(ちから)をぬいていきましょう^^
ここはまず、
【身体感覚】のやり方で、
“自分に愛を与えること”
を優先してみてもいいかもしれません。
“出したものが返ってくる”という法則は、
自分の内側でも同じように作用するので、
自分の内側が満たされるようになっていきます。
それが結果として
“他者に愛を与えること”
につながっていきます。
“愛されること”にこだわっていたり、
“愛すること”で負けたような気持ちに
なってしまうとき、
“愛すること”が自己犠牲のように
感じてしまうとき・・・
そんなときは
やっぱり自分への“愛”が足りていないときです。
ゆったりと力をぬいて、
自分に“愛”をgiveしていきたいですね^^
“愛”というとなんだか
ロマンチックで色気のあるものを
想像される方もいるかもしれません。
でも実のところ、
“愛”は深まるとドライになっていく
側面があるのではないかと感じます。
だからなのか、
そこかしこに散らばっているはずの
“愛”を見落としてしまうことがあります。
きっと
言葉にしたり形にされたものばかりが
“愛”ではありません。
そうした静けさのなかに
“愛”を見いだせるようになることも
人としての成熟のひとつであると感じます。
そのためには、
自分のなかで
“愛”の体感をどれだけ知っているか、
ということが求められるのかもしれません。
人から与えられる“愛”に
上がったり下がったり、
乱高下するようなものではなく、
穏やかでしなやかな…。
“内包するしなやかさ”とは、
全方位的に広がっていく“愛”の
起点となる自分への“愛”なんですね。
身体感覚の“気づき”は、
そんな【愛するための能力】を培ってくれます。